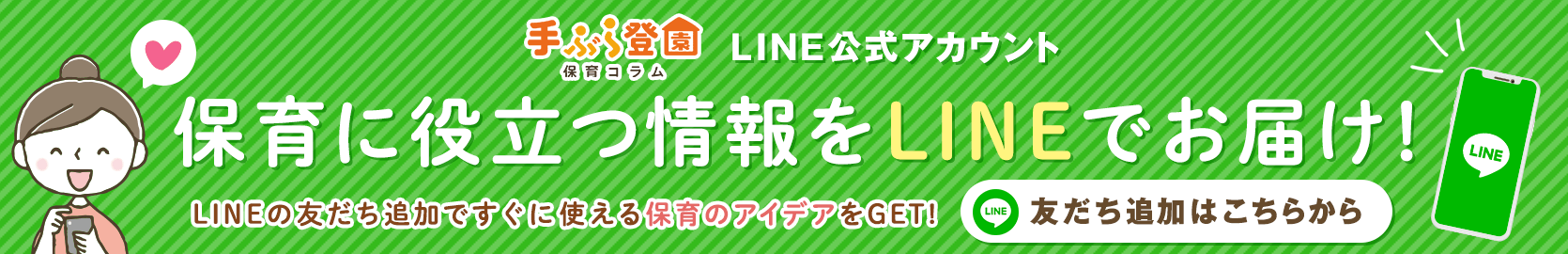保育の出し物「シアター」のおすすめ8選!演じるポイントも紹介!
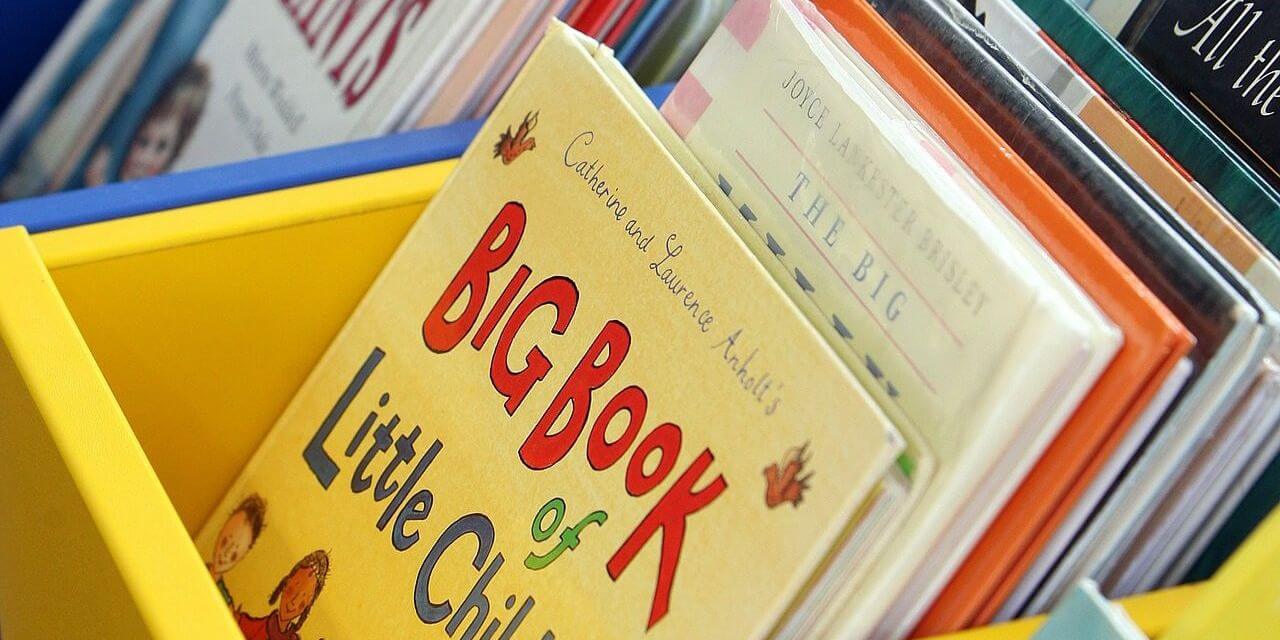
「そろそろ実習の準備しなきゃな・・・」
「絵本とは違うものを用意しておきたいな」
そんな時におすすめなのが「シアター」です。シアターは一度作っておけば万能なもので、保育のちょっとした隙間時間から誕生日会などのイベントの出し物まで幅広く活躍してくれます。子ども達も興味津々に見てくれることでしょう。
今回は、身の回りのものでも作れる簡単なシアターと演じる際のポイントをお話ししていきます。
保育の出し物「シアター」とは?
シアターとは、パネルや人形など、様々な道具を使って行われる劇のことです。「保育教材」とも呼ばれ、その種類は多岐に渡ります。以下に代表的なものを書いておきます。
- パネルシアター
- ペープサートシアター
- エプロンシアター
- 手袋シアター
- 紙皿シアター
- 紙コップシアター
- 色水シアター
- ハンカチシアター
- 段ボールシアター など
エプロンシアターや手袋シアターなど布を使った凝ったものもあれば、紙やペットボトル、ラップの芯など身の回りのもので作れるような簡単なシアターもあります。作りようによっては、何でもシアターに変身できるといっても過言ではないでしょう。
基本的には保育士1人で演じることが多いですが、演出の関係や話に幅を持たせるために複数で演じることもあります。絵本とは違い、大抵のシアターには動きがあるため子ども達も注目しやすいです。
これから保育士になろうとしている皆さんは「作るのが大変だな・・・」と思うかもしれませんが、保育実習の間だけではなく実際に保育士になった後も大いに活用ができます。就職した後ではなかなか作る時間も取れないため、時間のある時に作ることをおすすめします。
おすすめのシアター8選!
様々な種類のあるシアターは、一見作るのが大変だというイメージを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは身の回りのもので簡単に作れるシアターを8つ紹介します。
【新聞紙シアター】ピクニック
【用意するもの】
- 新聞紙1枚
【ポイント】
- 新聞紙1枚で進んでいくお話しであるため、演じる人の演技力が大切。適宜「これは何に見える?」と折った新聞紙の形を確認しながらおこないましょう
【画用紙シアター】金の斧、銀の斧
【用意するもの】
- 画用紙
- 折り紙
- はさみ
- のり
【ポイント】
- 場面の入れ替わりをスムーズにできると見やすいです
【スケッチブックシアター】なにがのび〜る!?
【用意するもの】
- スケッチブック
- 画用紙
- はさみ
- のり
【ポイント】
- 掛け声をかけた後、伸ばすところがメインです。1回目と2回目では伸ばす速度を変えてみるなど工夫しても面白いです
【スケッチブックシアター】ガチャガチャマシーン
【用意するもの】
- スケッチブック
- 画用紙
- クリアファイル
- はさみ
- カッター
【ポイント】
- ガチャガチャをした後、スケッチブックのページが入れ替わるところをスムーズにできると見ている方も自然な形で見ることができます。
【紙皿シアター】〇〇食べたのだぁれ?
【用意するもの】
- 紙皿
- 画用紙
- はさみ
- のり
【ポイント】
- 紙皿が回りながら絵が変わっていくところがポイントであるため、じっくりゆっくり回すと良いでしょう。
【ペープサートシアター】折り紙クイズ
【用意するもの】
- 厚紙
- 割り箸など持ち手になるもの
- 画用紙
- はさみ
- のり
- ペン
【ポイント】
- ヒントで後ろの絵柄を見せる時は、最初は見えないくらいに、徐々にゆっくりにすると盛り上がり楽しく見えるでしょう。
【ペープサートシアター】まほうのかさ
【用意するもの】
- 厚紙
- 画用紙
- 割り箸など持ち手になるもの
- はさみ
- のり
- ペン
【ポイント】
- 歌を歌いながらスムーズに進行できると良いです。
【色水シアター】おばけのジュース
【用意するもの】
- ペットボトル
- 絵の具
- 水
- 画用紙
- はさみ
- のり
- ペン
【ポイント】
- ペットボトルの本数を変えても良いでしょう
- 水を入れすぎると絵の具についてしまうため入れすぎないようにしましょう
シアターを演じる時の4つのポイント
シアターは道具を動かしながら演じるため少し難易度が高いと感じるかもしれません。しかし、以下のポイントを押さえておくことで見やすく楽しいシアターを演じることができます。
練習をしっかりしておく
リハーサルを十分にしておくことが大切です。流れを十分に確認しておくことで、気持ちに余裕を持って演じることができるでしょう。1番大切なのは、道具を動かしやすい位置や順番でできるように決めておくことです。手に取るだけにしておくと迷わずにできます。
また、「これは何かな?」「次は何が起きると思う?」と子どもたちに投げかける場所もあらかじめ決めておくと良いです。子ども達に質問しすぎるのは集中力が途切れてしまうためあまり良くありません。適度な場面で投げかけられるよう想定しておきましょう。
大きな声でゆっくり話す
年齢によっては、まだまだお話自体が理解しづらいこともあります。小さな声であったり、早口など何を話しているか分からないと子どもは面白くなくなり、集中力を失ってしまいます。そのため、大きな声でゆっくり演じることが大切です。時には間をもたせながら、子どもの反応を聞いてあげる時間を取ると良いでしょう。
反対に、部屋でホールで演じるように大きな声を出していてはうるさくなります。場所によって、声の大きさを変える工夫もしましょう。
動作にメリハリをつける
子ども達は動くものに注目し見ています。そのため、話しをしている登場人物を動かし、後のものは動かさないようにすると誰が今話しているか分かりやすくなるでしょう。
また、ゆっくり出てきて素早く引っ込めたり、跳ねるように動かしたりと動かし方をひと工夫するだけで、そのコミカルな動きを子ども達は面白いと思って見てくれます。これも練習の段階で十分に確認できると良いですね。
子どもとのコミュニケーションを大切にする

子ども達もシアターに参加できることでお話しの中に入り込み、その喜びや満足感も倍増します。
たとえば、登場人物が順番に出てくるのであれば「次は誰が出てくるでしょう?」などクイズ形式にすると良いでしょう。また、泣くシーンや戦いのシーンがあるようなお話の時は応援してもらう演出を入れても面白いかもしれません。
子どもとのコミュニケーションを大切に、お話の展開をスムーズにできると良いです。
シアターを覚えて、充実した実習を迎えよう
保育の出し物であるシアターには、様々な種類があることが分かりました。簡単に作れるものから難しいもの、小さなものから大きなものまであるため、自分に適したものを選んで作ると良いでしょう。
また、シアターは演じ方が大切です。子ども達の前でおこなうことは緊張するかもしれませんが、失敗を恐れず堂々とおこなうことで子ども達もお話の世界を楽しんでくれます。今から準備を進めて、ぜひチャレンジしてみましょう。