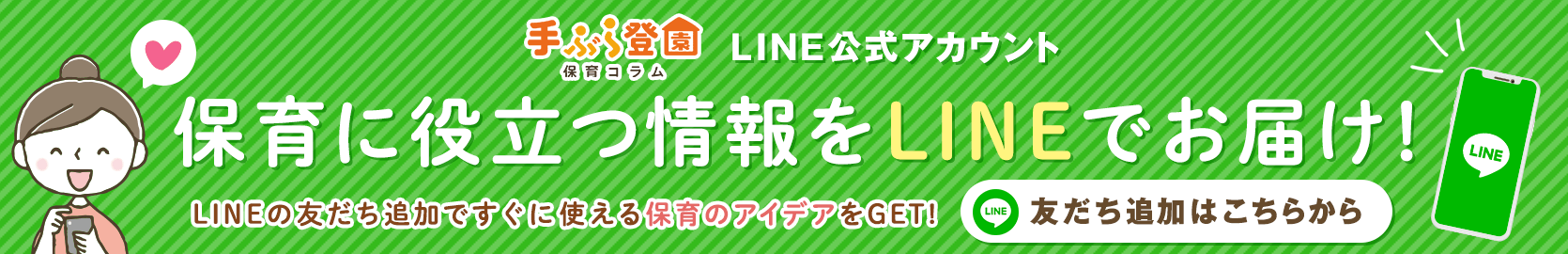保育園でおすすめの簡単手品10選!成功させるポイントも解説!

大人から子どもまで盛り上がる手品。保育園でもおなじみの出し物ですが、見たことはあっても自分で手品をするのは初めてという方も多いのではないでしょうか。
「テレビで見る手品はどれも難しそうだな・・・」
「子どもでも分かるような簡単な手品が知りたい!」
と悩む方のために、今回は簡単で盛り上がる手品を厳選しました。また、手品をする時のポイントについてもお話ししていきます。
保育園でおすすめの簡単手品10選!
まずはおすすめの手品をご紹介。どれも少しの練習で習得できるため、忙しい仕事の合間でも気軽に覚えることが出来ます。それぞれのポイントも参考にしながらおこなってみましょう。
勝手に動くハンカチ(0:00〜)
【用意するもの】
- ハンカチ
【ポイント】
- ハンカチを曲げた時に引っ張るなど、右手の左手の動きを合わせるようにします
- ストーリー性を大切にします
なんでも出てくるハンカチ(0:06〜)
【用意するもの】
- ハンカチ
- 鉛筆やペン
【ポイント】
- 腕から鉛筆やペンが見えないようにします
- ハンカチにタネもしかけもないことをしっかり見せます
破れたはずの新聞紙が元どおり?!(2:30〜)
【用意するもの】
- 新聞紙2枚(破る用・元に戻る用)
- 両面テープ
【ポイント】
- はじめに新聞紙を見せる時は、折りたたんだ新聞紙が見えないよう表だけを自然な形で見せるようにしましょう
- 丸めた時に手の動きを工夫し、自然な形で新聞紙が入れ替わるようにする。鏡などで見ながら練習すると分かりやすいです
水がこぼれない不思議な新聞紙(1:08〜)
【用意するもの】
- 新聞紙
- 紙コップ2個(片方は半分の大きさに切っておく)
- 水
【ポイント】
- 紙コップの動きが重要です。特に後ろに忍ばせた紙コップを普通の紙コップにいれる時の手の動きが自然な形になるようにします
- 新聞紙を傾けると見えてしまうため、傾けないよう注意しましょう
復活する風船(0:33〜)
【用意するもの】
- 風船2つ
- はさみ
【ポイント】
- 最初に風船を小さく詰める時、ほどけてこないようしっかり詰めましょう
- 子どもを1人呼び、実際に切ってもらっても良いでしょう
カップとピンポン玉(1:32〜)
【用意するもの】
- 紙コップ3つ(うち1つは切り込みをいれる)
- ピンポン玉など紙コップに入るもの
【ポイント】
- 斜めに持ち上げてしまうと中身が見えてしまうため、真っ直ぐ持ち上げましょう
絵のコーラが本物に!(0:30〜)
【用意するもの】
- 絵を描いたスケッチブック
- 切り込みを入れる用のはさみかカッター
- コーラ
【ポイント】
- 後ろで持っているコーラが見えないよう手さばきを練習しましょう
- 導入として、いくつか飲み物の絵を見せてシアターのようにするのも良いでしょう
ペットボトルに入るコイン(2:43〜)
【用意するもの】
- 空のペットボトル
- 小銭
- カッター
- セロハンテープ
【ポイント】
- コインをいれる時に、穴が空いているところを入れやすい位置に移動させます
- 少しゆっくりとコインをいれることで貫通しているように見えるでしょう
首が回るイリュージョン!(0:00〜)
【用意するもの】
- 段ボール
- はさみかカッター
【ポイント】
- 段ボールを回す人、首を回す人の息を合わせるようにします(2人でやる場合)
- 穴が大きすぎると中が見えやすくなってしまうため、顔のサイズ程度にしておきましょう
水の色が一瞬で変わる!(0:00〜)
【用意するもの】
- ペットボトル
- 絵の具
- 画用紙
- はさみ
【ポイント】
- 水を入れすぎると、絵の具にあたって水に色がついてしまいます
- ストーリーによって使う絵の具やペットボトルの本数を変えても良いでしょう
保育園でおこなう手品の選び方とは?
子どもの前でおこなう手品は、見やすく分かりやすいものであることが大切です。ポイントを押さえて手品を選ぶことで、子どもの注目を集め続けながら手品を盛り上げることができるでしょう。
道具は身近にあるものでやろう
道具は段ボールや画用紙、ハンカチなど身近ですぐに手に入るものを使うと良いです。第1に、準備にお金がかかりませんし、素材が分かることで子どもが「あれ知ってる!」と興味を持つからです。
手品の道具は既製品を探そうと思えば多くのものが手に入ります。既製品の方がしかけもしっかりとしているので安心してできるでしょう。しかし、子ども達に親しみのある身近なものであえて手品をすることで、より子ども達は不思議さを感じたり驚いたりするのではないでしょうか。
また、後に子どもが遊びの中でまねする時も、用意しやすく作りやすいかもしれません。年齢が大きくなればなるほど、見たものを忠実に再現したいのが子どもです。同じ素材であることで、子ども自身の満足につながります。
時間が短いものをいくつか用意しよう
幼児期の子どもの集中力は年齢プラス1分と言われています。1番大きな年長児であっても、論理上は7分程度しか集中力がもたないということです。そのため、子ども向けのテレビ番組はその集中力に合わせてコンテンツがコロコロと変わるように出来ています。
保育の出し物は大体10〜20程度であることが多いです。その中で子どもが最後まで飽きないようにするため、短めの手品をいくつか用意して披露すると良いでしょう。
ただし、上記で紹介した色水シアターのように物語性のあるものは集中力が続きやすいです。この場合は、他の手品をするのであれば1〜2つにしておき、メインの手品に十分集中が向くようにしましょう。
大きな演出のものを必ず入れよう
出し物は部屋の中でおこなうこともあれば、ホールでおこなうこともあります。ホールの場合、正面に近い子は良いですが、並ぶ関係上どうしても遠くから見る子も。
そのため小さな演出ばかりでは子どもの集中力が切れてしまう可能性があるため、上記の「首が回るイリュージョン!」のようにしっかり見える大きな道具のものもやってみましょう。
ただし、風船を割るなど大きな音が出る演出は、赤ちゃんがびっくりしてしまうためあまり好ましくありません。準備するものの大きさ、声の大きさ、物の動かし方を工夫し、演出に緩急をつけることが大切です。
保育園での手品を成功させる4つのポイント
せっかく練習したならば、見ている子ども達に喜んでもらえるような手品をしたいですよね。準備の段階から本番のちょっとしたテクニックまで、以下の4つの事を意識するだけで大成功に導くことができるでしょう。
いつもと違う雰囲気を演出しよう
手品をはじめる前の演出にも工夫をしてみましょう。例えばBGMを普段と変えてみたり、衣装を手品師のようにしてみたり、鼻メガネなんか用意すると子どもの興味を引くことができます。
また、子ども達の後ろから登場するなど、いつもとは違うところから登場すると子ども達も驚き「何が始まるのかな?」とワクワクしてくれることでしょう。
手の動かし方を意識しよう
手品は手の動かし方が全てといっても過言ではないくらい大切です。見ている人の興味を引くだけではなく、隠している物をバレないように動かすためにも自然な形で手を使いたいです。
人は動くものを目で追う習性があることをご存知でしょうか。隠したいものと反対の手を動かしておくことで、見ている人は反対の手の方に集中しタネがバレにくくなります。このようにひと工夫することで、手品の成功率がぐんと上がるでしょう。
子どもとのコミュニケーションを大切にしよう
子ども達は、参加をすることで喜びを感じ、満足感を得ることができます。何かを持ってもらう手伝いをお願いしたり、タネがないことを確認してもらう演出も良いでしょう。
簡単なのは「これは何かな?」「次はどうなると思う?」と言葉がけをしていくことです。すると子ども達は自分なりに「ペットボトル!」「消えちゃうんじゃない?」などと反応してくれることでしょう。子どもも質問を考えることで、理解しやすくなるメリットもあります。
また、ときにはマジックをわざと失敗してみるのはどうでしょうか。「先生がんばれー!」と応援してもらう演出をいれることで、より一層自分が参加出来たという満足感を子どもは持ちやすくなります。
見やすい演出を工夫しよう
これは普段から気にしていることかもしれませんが、マジックも大前提として子どもが物事を理解出来ているかどうかが大切です。年齢による理解度の違いは仕方のないことですが、そもそも小さな動きで見えない!となると子どもは不満に思い、集中力を切らせてしまいます。
身振り手振りを大きくしたり、ゆっくり話すようにする、小さな道具は手品をはじめる前に全員の近くに行って見せるなど、基本的な部分は理解できるよう配慮をしましょう。
保育園で手品を披露してみんなで盛り上がろう!
子ども達は分からないこと、不思議に思うことが大好きです。「なんでだろう」と思う気持ちを好奇心に変え、皆さんがおこなう手品をキラキラとした目で見てくれることでしょう。
今回ご紹介した手品はどれも覚える時に分かりやすく、簡単なものばかりです。出し物が終わった後に、子ども達と一緒におこなってみるのも良いですね。手品を披露して、子ども達と楽しいひとときを過ごしましょう。