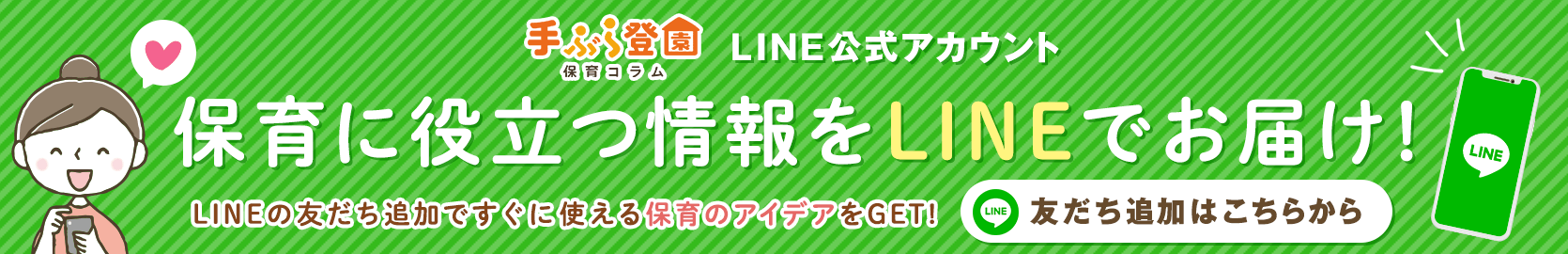保育における環境構成とは?環境作りのねらいと配慮ポイント

保育実習の部分実習や責任実習をする際、指導案を書きながら気になるのが「環境構成」です。
実際に保育園で働き始めてからも、週案や月案を立てるときに、環境構成がいつも同じような内容になって、「これでいいのかな?」と疑問に思っていませんか。
子どもは環境の中で成長・吸収し、学んでいくので、保育の中でも環境構成はとても大切です。
環境によって子どもの反応や成長が大きく変わってきますので、しっかり理解して、実践につなげましょう。
この記事では、
- 保育における環境構成とは
- 環境構成について配慮するポイント
- 環境構成の具体例
の3点について、以下詳しく説明します。
保育における環境構成とは

「環境構成」とは、「人・物・場」などの環境を、子どもたちの成長・発達に合わせて工夫し、子どもたちの園生活が豊かなものになるように構成することです。
保育の環境は、
- 人的環境
- 物的環境
- 自然環境
- 社会的環境
の四つが、相互に関連し合って作り出されています。
保育士は、環境の中でさまざまな相互作用が働くことにより、子どもが成長・発達することを理解し、
- 子どもからの働きかけに応じて柔軟に変化する環境
- 周囲の状況に合わせてさまざまに変化する環境
を、保育に取り入れていくことが大切です。
はじめに、四つの環境について詳しく見ていきましょう。
保育の環境「人的環境」
「人的環境」とは、担任の保育士や他の保育士など、保育園に関わる職員の人柄や言動、間関係や雰囲気のことです。
1番身近な手本となるので、その一つひとつの言動に気を配ることが大切です。
また、保育士同士のが仲がよく、和やかな雰囲気であれば、保育園があたたかな落ち着く雰囲気になり、子どもたちも安心して過ごせます。
保育の環境「物的環境」
「物的環境」とは、園庭・園舎・遊具・設備・玩具・絵本・紙芝居など、物理的・文化的な物のことです。
保育園の園舎や保育室、園庭などは、活動が十分できるような広さや設備で、子どもが自発的に活用できることが重要です。
集団で生活する場として、掃除や洗濯など、清潔を保てること。ドアの開閉で手を挟まないようにしたり、机の角などでケガをしないよう事故防止がされていることも大切な環境といえます。
保育の環境「自然環境」
「自然環境」とは、園庭や園周辺の自然、また海や山、太陽や月、季節など自然の環境のことです。
園の畑で農作物を栽培したり、飼っている虫や動物などと触れ合うことで、命の大切さ・優しい思いやりなどを育めます。
保育の環境「社会的環境」
「社会環境」とは、地域の住民とのふれあいや、公共施設で社会と触れ合うことです。
地域のお年寄りから昔の遊びを教えてもらったり、絵本の読み聞かせボランティアグループのお話会を楽しんだり、近所の美術館見学をしたりするなど、保育園の中だけではできない経験のことをさし指します。
次は、環境構成について、配慮するポイントを見ていきましょう。
環境構成について配慮するポイント
環境構成を考えるときに配慮し、意識すべきポイントは、以下の4点です。
- 子どもが自発的に活動し、経験を積める
- 子どもの健康と安全を守る設備や環境である
- 静と動のバランスが取れた活動に取り組める
- 子どもがさまざまな人と関わる力を育む
これらのポイントについて、以下、具体的に紹介します。
自発的に活動し経験を積める
子どもが自分から環境に関わり、自発的に活動し、さまざまな経験を積んでいくことができるように配慮しましょう。
子ども自身の興味や関心が刺激され、「なんだろう?」「やってみたい!」と、自分から関わりたくなるような、子どもにとって魅力ある環境を保育士が構成することが重要です。
また遊びが展開する中で、子どもが自発的に環境を作り替えていくことや環境の変化を、子どもたちとともに保育士自身も楽しみ、思いを共有することが大切です。
保育園内の環境や自然環境などを生かしながら、豊かな環境を構成するようにして、子どもの経験が偏らないように 配慮しましょう。
子どもの健康と安全を守る
子どもの健康と安全を守ることは、保育園の基本的で重大な責任です。
子どもの活動が豊かに展開していくように、保育園の設備や環境を整えて、保育園の保健的環境や安全の確保をします。
また子どもの命を守り、その活動を支えていくために、衛生や安全の管理等について、全職員が意識統一し、常に配慮していくことが重要です。
静と動のバランスが取れた活動に取り組める
保育室が温かく親しみとくつろぎの場になり、子どもがイキイキと活動できる場となるように配慮しましょう。
子どもの心身の健康と発達を支えるよう、保育園での一日の生活が、子どもの発達や季節などに応じて、静と動のバランスの取れたものになるように配慮することが重要です。
保育園生活で、子どもが保育士と一緒に落ち着いて過ごしたり、くつろいだりすることのできる時間や空間を作りましょう。
- 一人または少人数で遊びに集中する
- 友達と一緒に思い切り体を動かして遊ぶ
- さまざまな活動に取り組むことができる
など、遊びや活動が活発で豊かに展開するよう、配慮や工夫をすることが必要です。
さまざまな人と関わる力を育む
子どもが人と関わる力を育むために、子どもが自分から周囲の子どもや大人と関わっていける環境を整えましょう。
子どもは身近な人との関わりから影響を受けて育つので、同年齢の子ども同士の関係、異年齢の子どもとの関係、保育士等との関係や地域のさまざまな人との関わりなど、安心してさまざまな人と関わる状況をつくり出すことが重要です。
友達と一緒に遊べる遊具やコーナーなどを設定したり、大人数でもスムーズに活動できるよう、導線を考えた物の配置をしたりすることも大切です。
子どもが人とのやり取りを楽しみ、子ども同士や周囲の大人との関わりが自然と促されるような環境を作っていきましょう。
環境構成の具体例

子どもが自発的に活動し経験を積むような保育をするうえで、環境構成はとても大切です。
保育計画を立てる際は、
- 何をどのように置いておけば、子どもたちが興味を持つだろうか
- 何を使えば子どもたちの遊びが深まるだろうか
- 子どもたちの活動が自然に展開するには、どのような導線を引いておくといいだろうか
というように、それぞれの活動の「ねらい」を達成するために必要な物を書き出し、環境構成を考えていくとよいでしょう。
また日誌に記載する場合は、机の位置や材料を置く場所など、図を使って書くとわかりやすいです。
以下、遊びにおいての具体的な環境構成の例を挙げます。
室内遊びの環境構成
- 絵本・ごっこ遊び・ままごと・製作などのコーナーを作り、それぞれ使いやすく片付けやすいように整理する(動きの導線も考える)
- ブロックなど、破損した物はないか確認し、乳児が遊ぶ玩具は消毒などもこまめに行う
- 全身を動かす活動のとき、たとえばマットや、室内でも使えるボールなどを使用するときはそれぞれの活動がしやすい配置に置く
戸外遊びの環境構成
- 遊具や用具の破損がないかを点検・確認しておく
- ゲームをする際、園庭にラインを引く必要があれば、あらかじめ引いておいたり、導入として子どもの前で引いたりする
- 暑くなる時期は、気温や日差しなどに気をつけ、水分を摂ったり、日陰で遊んだりするなど、熱中症対策をする
- 砂場遊びで、子どもが使いたいと思った玩具や遊びに使える物がすぐに取り出せるよう、砂場のそばに準備をしておく
製作の環境構成
- 製作と関連する自然物や絵本・図鑑などを、子どもたちのよく見える場所に置いておき、興味や関心が持てるようにする
- 製作に必要な色画用紙や折り紙などの材料は、前日までに人数分揃えて、グループごとに分けておく
- 絵の具を使った製作では、絵の具で塗る場所・乾かす場所・筆やパレットを洗って乾かす場所に移動する導線がスムーズか、子どもが次の行動をしやすい配置を考えておく
まとめ
以上、この記事では、
- 環境構成とは
- 環境構成について配慮するポイント
- 環境構成の具体例
の3点について、詳しく説明しました。
子どもの発達や興味関心に応じて環境を構成することにより、子どもたちは自発的・意欲的に活動をし、さまざまな経験を積むことができます。
環境構成について配慮するポイントを意識しながら、それぞれの活動の「ねらい」を達成するために必要なものを考え、子どもたちがイキイキと過ごせるような環境構成をしていきましょう。