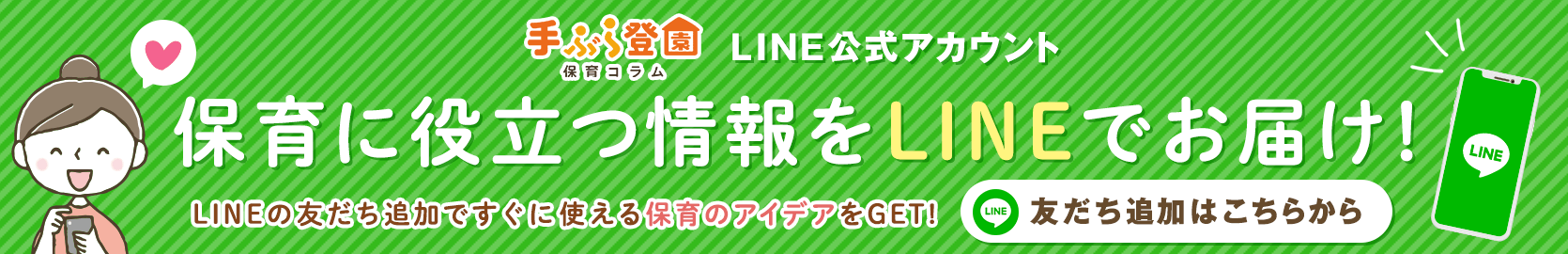保育で盛り上がるゲーム遊び10選!遊び方のポイントを紹介

雨の日が続くときや、暑さや寒さが厳しい季節は室内で遊ぶ時間が増えます。
室内で遊ぶ時間が増えると悩むのが、新しい遊びのネタです。
毎回同じ遊びをしていたら子どもたちも飽きてしまいますし、興味の幅を広げることもできません。
その問題を解決するためには保育士がたくさんの遊びを知り、子どもたちに教えてあげることが大切です。
とくに、ゲーム形式の遊びは勝ち負けがつくドキドキハラハラと刺激が強く、子どもたちから好評を得られやすいです。
普段の遊びがマンネリ化してきたと感じたら、新しい遊びのネタとして積極的にゲームを取り入れていきましょう。
ゲーム形式の遊びのメリット

ゲーム形式の遊びには、以下のようなメリットがあります。
- 言葉を交わすことによりコミュニケーション能力を高める
- ルールの中で勝つための方法を考える
- 紙芝居や積み木などに比べ、実践的な緊張感を得られる
ゲーム形式の遊びでは、勝ち負けを明確にしたり、賞品を設定したりするとさらに白熱して飽きづらくなります。
園独自でアレンジを考えるとみんなが楽しめるルールにより近づけますので、子どもたちと試行錯誤してオリジナルゲームを生み出しましょう。
保育園で盛り上がるゲーム遊び10選
しっぽ取りゲーム【2~5歳向け】
<遊び方>
- 先生は人数分のタオルや新聞紙でしっぽを用意し、子どもたちが走り回れる範囲を決める
- 子どもたちのズボンにしっぽを入れる
- 先生が「よーいスタート!」の合図をしたら、子どもたちは自分のしっぽを取られないように走る
- しっぽを取られてしまった子どもは、範囲の外に出る
- 最もしっぽを多く取った子どもが勝ちになります。
このゲームは大人数になるほど盛り上がる傾向があります。
走り回れる範囲や制限時間を決めて遊ぶことで、自分のいる位置や残り時間に応じてメリハリをつけて遊ぶことができます。
しっぽをズボンの中に入れすぎると取りづらくなるので注意してください。
こんなこと♪こんなこと♪できますか?【3~5歳向け】
<遊び方>
- 保育士が前に出て子どもたちと向かい合う
- 保育士は「こんなこと、こんなことできますか?」と言いながら動作のお題を出す
- 子どもたちは「こんなこと、こんなことできますよ!」と言いながら保育士の動作をマネする
- 慣れてきたら子どもたちにもお題を出してもらいましょう。
さまざまな動作がありますが、人気キャラクターの特徴的な動きをマネするのも盛り上がります。
リズムを速くしたり、複雑なお題を出すなどの工夫をすると難易度が上がり、飽きずに長く楽しむことができます。
おちたおちたゲーム【3~5歳向け】
<遊び方>
- リズムに合わせ、おちてきたものによってリアクションを変える
- 雷が落ちたらおへそがとられないようにおへそを隠す
- げんこつが落ちてきたら殴られないように頭をガードする
- リンゴが落ちてきたらキャッチして食べる
オリジナルのものが落ちてきたり、リアクションにアレンジを加えることでより楽しめますし、難易度を調整することもできます。
色探しリレー【3~5歳向け】
<遊び方>
- 先生が色を探せる範囲を決め、色を1つ指定する
- 先生が「〇〇の中で◯色はどれでしょう、よーいドン!」と呼びかけ、子どもたちは指定された色を探す
- 何回かやったら曲をながして曲が終わるまでに探すなど、制限時間を作ってチャレンジしてみる
楽しみながら色の種類や名前を覚えられます。
ルールがシンプルでわかりやすく、幼い子も一緒に遊べるので、クラス全員で楽しめます。
ジェスチャーゲーム【3~5歳向け】
<遊び方>
基本の遊び方の場合
- 子どもたちをいくつかのチームに分けて、1人解答者を決める
- 解答者以外の子どものなかで順番を決める
- 先生はお題が書かれた紙を解答者以外の子どもたちに見せる
- 子どもたちは身体を使ってお題を表現し、解答者に答えてもらう
- 解答者が全員分のお題を正解できたチームが勝ち
リレー式の場合
- 全員が解答者になる
- 1番目の子がジェスチャーをして2番目の子が答える
- 2番目の子が正解したら3番目の子に向けてジェスチャーをし、3番目の子が答える
- この動作を順番に繰り返す
子どもたちにとって身近なものを出題することが、このゲームを盛り上げるポイントです。
徐々にお題の難易度を上げていくと盛り上がります。
沈没ゲーム【4、5歳向け】
<遊び方>
- お部屋の中を海にみたて、マットやフラフープなどで船を用意する
- 先生がサメになり、子どもたちは船に待機する
- 先生が沈没と言ったら子どもたちはサメに捕まらないようにほかの船に移動する
沈没とよく似た語感のフェイクワードを使うと、子どもたちが騙されるので盛り上がります。
また、声をわざと小さくすると子どもたちは聞き漏らさないように集中してくれるので、言葉を注意して聞く力も養われます。
◯✕クイズ【4、5歳向け】
<遊び方>
- 〇の範囲と✕の範囲を作る
- 先生が〇か✕で答えられるクイズを出題する
- 子どもたちは問題が正しいと思ったら〇の範囲に移動し、間違っていると思ったら✕の範囲に移動する
生活や遊びのなかのルールを覚えたり、理解するきっかけになるので教育にも効果的です。
保育園や行事に関することを◯✕クイズのお題にすれば、子どもたちに身近なことなので答えやすくなります。
間違えた場合でも、ゲーム感覚で楽しみながら学ぶことができます。
別の日に同じ問題を出せばおさらいにもなって、前回は間違えた問題を正解したときに成功体験を感じられます。
信号ゲーム【4、5歳向け】
<遊び方>
- 横断歩道を子どもたちに渡ってもらう
- 青といった場合は一歩足踏みをする
- 黄色といった場合は首を振って「キョロキョロ」と言う
- 赤といった場合は素早くしゃがむ
- 赤、青、黄色以外の色が呼ばれた場合は「な~いない」と言う
色とは関係ないフェイクワードを用意すると盛り上がります(フェイクワードのときは赤信号と同じ)。
交通ルールを楽しく覚えることにも効果的です。
宝探しゲーム【4、5歳向け】
<遊び方>
- 宝物を子どもたちに見せる
- 子どもたちに目をつぶってもらい、その間に宝物を隠す
- 隠し終わったら「目を開けていいよ。よーいスタート!」と子どもたちに呼びかけ、宝物を探してもらう
- 最初に宝物を見つけた人が勝ち
宝物にするアイテムは、見つけやすい色や大きさの物を用意しておきましょう。
アレンジルールとして複数の宝物を用意して点数制にしたり、見つけた数を競ったりしても面白くなります。
もうじゅうがり【4、5歳向け】
<遊び方>
- リズムに合わせて動物の名前を呼ぶ
- 呼ばれた動物の名前の文字数と同じ数のグループを作る
- グループができたら座り、あぶれた子はみんなの前で動物のものまねをする
動物の名前を呼ぶときのポーズをアレンジすることで子どもたちの注目を集めることができます。
一人だけだと恥ずかしい子もいるので、ものまねをやりたい子たちも前に一緒に誘いましょう。
まとめ

外で遊ぶ機会が減り、体を動かせない子どもたちはストレスが溜まっているでしょう。そんなときだからこそ、考えて動いて楽しめるゲーム遊びは効果的です。
外遊びをする機会が少なくなる時期でも、子どもたちと楽しい時間を過ごせるようにしましょう。