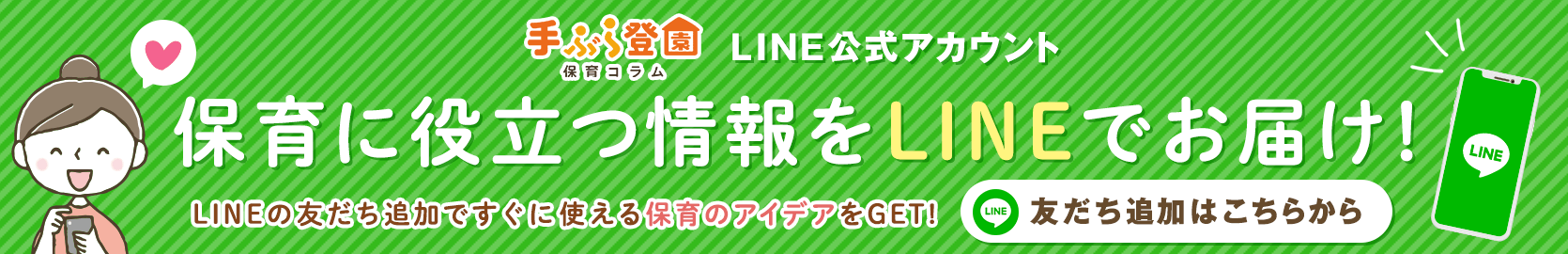保育記録は効率良く書ける!ICT化で園全体の質をUPしよう!

日々成長する子どもたちの様子を記録するために必要不可欠なのが「保育記録」です。保育記録は、保育士同士や保護者とのやり取りの中で、重要な役割を果たします。
しかし、慣れていないと保育記録の書き方がわからなかったり、時間がかかったりしてしまうため、保育士の中には苦手意識を持つ人も出てくるでしょう。
この記事では、保育記録の意味や書き方、早く書けるようになるコツをご紹介します。記録時間を短くし、子どもとの時間を大切にできるよう、効率良く書く方法を保育士に共有しましょう。
保育記録とは
保育記録とは、1日の終わりに今日あったクラスの出来事や園児の様子などを記したものです。記録した内容を活かすことで、今後の保育をより良いものにするという目的があります。
毎日の記録の中から、課題や問題点が見つかることも多いです。
しかし、保育記録は毎日書くものなので、ただでさえ忙しい保育士にとっては負担に感じる部分もあるでしょう。また、クラスごとではなく、子ども一人ひとりの記録を毎日書かなければならない場合もあります。
保育記録の内容は全国共通というわけではありません。基本は園ごとに項目が決まっており、以下のような内容を記載することが多いです。
- 日付、天気
- 園児の出欠状況、欠席の理由
- 園児の健康管理
- カリキュラム、行事
- 保育のねらいと保育内容
- 園児の様子
- 保護者への連絡
- 問題点や気づいた点など
保育記録の効率的な書き方
現場の保育士がそもそも文章を書くことが苦手だったり、慣れていなかったりすると、保育記録の作成に時間がかかります。
忙しい現場を上手に回すためにも、保育記録の効率的な書き方を共有し、働きやすい職場作りを心掛けることが重要です。
ここからは、保育記録の書き方のコツを6つのステップに分けてご紹介します。短時間で書き終わっても内容が乏しければ意味がないため、保育記録は効率と内容どちらも大切にしながら書きましょう。
①園独自の項目を確認する
大元はどこの園も似ていますが、園によって保育記録の項目が多少変わる場合があります。
経営者や責任者が項目を決めるため、保育理念が似ている園などを調べた上で、独自の項目を設定しましょう。
保育士には項目をしっかりと確認してもらい、実際に何を書けば良いか事前にわかるよう伝えておくとスムーズです。
②要点を押さえてメモを取る
園独自の項目がわかれば、何をメモすれば良いかもわかってきます。メモを取るときは、文章ではなく単語で書き出し、後で見返したときに思い出せるようにしましょう。
どうしても忙しく、ついメモを取るのを後回しにしてしまう場合は、メモを取る時間を前もって決めておくと、毎日のルーティーンにできます。
あくまでもメモなので、時間をかける必要はありません。自分が読んで、理解できれば大丈夫です。
③テンプレートを使用する
文章を書くのが苦手という人でも、テンプレートを使用するだけで、簡単に記録が書けるようになります。
テンプレートはオリジナルで作っても良いですが、インターネットで検索をかけると、簡単に保育記録用のテンプレートが出てくるので活用しましょう。
実際にいくつか使ってみて、書きやすいと思ったものを使用してみてください。少しでもテンプレート部分を増やすことで、記録を早く終えることができます。
ただし、テンプレートの選択肢が多すぎても選べなくなるので、責任者が1つか2つを選び、現場で働く保育士に提案すると良いでしょう。
④読みやすい文章を作る
保育記録は毎日書いただけで終わりではありません。後で見返し、今後の保育に役立てることが目的なので、読みやすくわかりやすい文章を書くことが重要です。
読みやすい文章を書くためには、以下のことを心がけましょう。
- 5W1Hを意識する
- 箇条書きにする
- 短い文章にする
- 同じ文末表現を連続させない(「子どもが遊んでいました。子どもは楽しそうでした。」など)
文章力は保育士でなくても必要です。読みやすい文章の書き方を覚えておいて損はありませんので、コツを掴んで徐々に慣れていくと良いでしょう。
⑤具体的な内容を入れる
特定の子どもの様子を記録する場合は、より具体的な内容を入れます。例えば「ケンカをしていた」ではなく「どのようなケンカなのか」、「どのように解決したのか」といった情報を具体的に書くことが大切です。
具体的な内容にすることで、今後の保育目標が立てやすくなったり、子どもの成長を感じられたりします。
⑥誤字脱字、記入漏れのチェックをする
誤字脱字や記入漏れがあるだけで、保育記録は「適当に終わらせた」や「記録の重要性がわかっていない」という印象になってしまいます。
主語と述語の関係性が成り立っていなかったり、文章が長すぎて読みにくかったりすることもあるので、記入後には必ず読み返しましょう。
最初から最後まで文章を確認し、おかしい部分はないか必ず確認してください。保育士一人ひとりが徹底して行うことで、取りまとめる園長もチェックがしやすくなり、問題点の解決に多くの時間を使うことができます。
ICT化による保育記録のメリット
ICTとは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略で、インターネットを利用することで、人と人や、人と物をつなぐことを表します。
今までは手書きで記録をつける園が多く、なかなかインターネットを導入する機会がありませんでした。
しかし、インターネットを導入することで、現場の作業が軽減され、その分子どもたちに向き合う時間を多く取ることができます。最後に、ICT化による保育記録のメリットをご紹介します。
入力項目が減る
子どもたちの基本情報や出欠状況は既に登録されているため、実際の行動を中心に入力していきます。文章のテンプレートもあるため、文章力に自信がないという人でも安心です。
過去の保育記録も簡単に参照できるため、参考になる文章をコピーして、自分の言葉に書き直すこともできます。ICT化により、実際に手打ちする入力項目が減るのが特徴です。
共有しやすい
インターネットを利用して作成した保育記録は、電子データとしてクラウド上に保存してあるので、パソコンやスマホ、タブレットからいつでも見ることができます。
そのため同じクラスの記録だけでなく、他クラスの記録も簡単に閲覧でき、園全体の把握がしやすいです。
保育記録初心者の場合は、参考として先輩の記録に目をとおすこともできます。データを簡単に共有し、参照できることが、ICT化による大きなメリットです。
ペーパーレス化につながる
保育現場では、折り紙や新聞紙、画用紙などの紙を使った保育が多く行われます。毎日必要な保育記録が紙媒体から電子データになるだけで、ペーパーレス化につながり、経費削減になるのでおすすめです。
経費を削減することで、その分実際の保育現場で必要なものの購入費用に当てることができます。
保育ICTシステムと連携して使える「手ぶら登園」

手ぶら登園は、煩雑なおむつ管理を効率化する月額定額制のおむつお届けサービスです。
「おむつ1枚1枚に名前を書く」、「園児ごとにおむつを管理する」といった、保護者・保育士が煩わしく感じている作業をなくし、忙しい毎日にゆとりを作ります。
保育ICTシステムで有名なコドモン・Hoisysとシステム連携を行っているため、いずれかを既に導入済みの園なら手ぶら登園もスムーズにご利用いただけます。もちろん、手ぶら登園のみを利用することも可能です。
手ぶら登園について気になる方はこちらから詳細をご確認ください。
まとめ
保育園の経営者や園長は、子どもたちや保護者だけでなく、働く保育士にとっても良い環境作りを目指さなくてはなりません。
保育記録の作成にかかる負担を軽くするためにも、何を書くか、どう書くかというポイントを押さえましょう。いかに効率良く記録を残すことができるかが重要です。
さらにICT化することで、より早く作業ができるようになり、保育士の負担を減らせます。経営者・保育士・子ども・保護者全体の満足度を上げるために、まだICTを導入していない園でも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。