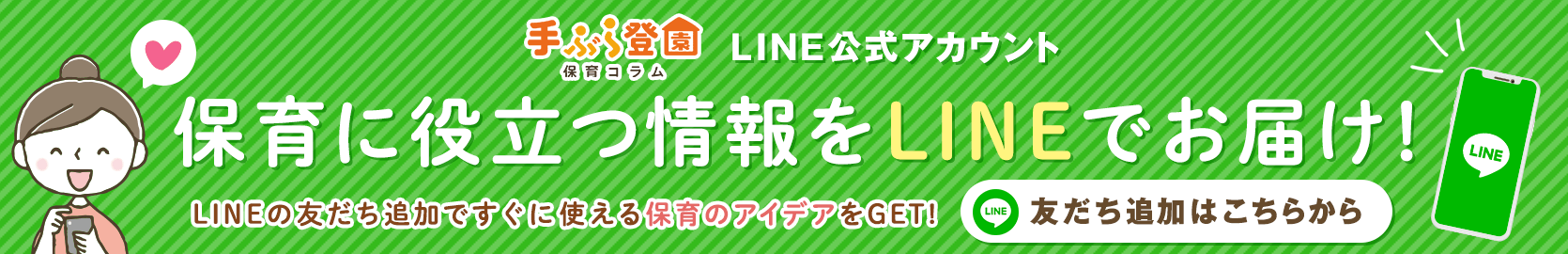保育でおすすめの室内遊びを年齢別に紹介!

梅雨や寒い時期には、室内遊びが多くなりますよね。毎日室内にいると「今日は何をしようか」とアイディアが浮かんでこない日もあるでしょう。
今回は、室内遊びを乳児・幼児別に紹介していきます。
保育での室内遊びは発達に合ったものを
室内遊びといっても、種類はさまざまあり、目的によって変わってきます。
たとえば、
- 体を動かす「運動遊び」
- 考える力を養う「ゲーム遊び」
- 指先の機能を高める「手先の遊び」
- 音を楽しむ「楽器遊び」
- 創造力をつくる「製作遊び」
など。
年齢の発達に見合った遊びを行うために環境を整えることが重要です。
保育でおすすめの室内遊び【乳児向け】
乳児期はまだ、ひとり遊びが多い時期です。室内遊びを通して、指先の機能を高めたり、友達と遊ぶことの楽しさなどを学んでいきます。
年齢別にみていきましょう。
0歳児
つかまり立ちやハイハイができるようになり、探索行動が活発になる0歳児の時期。
人に愛着をもつことや、五感を刺激することが主なねらいになります。
- 保育者とスキンシップをとるなかで、信頼関係を築いていく
- 身体を動かす楽しさを知る
- おもちゃや手遊び、わらべうたなどを通して五感を育む など
0歳児におすすめの室内遊びを紹介します。
ハイハイ鬼ごっこ
ハイハイは、腕の筋力を鍛えるために大切な運動です。ハイハイで動き回れるようになったら、保育士も「まてまて」と鬼ごっこのように追いかけ、一緒にハイハイをします。
運動とスキンシップを取り入れられるおすすめの遊びです。ただ、勢いがよすぎると子どもが転んでしまう可能性もあるので、安全には十分配慮し、穏やかに楽しく行いましょう。
ふれあい遊び
ふれあい遊びは、リズム(聴覚)や手の動き(視覚)などの五感を刺激できるだけでなく、コミュニケーションもとれるため、0歳児に最適の室内遊びといえます。
*あがりめさがりめ|ゆめあるチャンネル
*一本橋こちょこちょ|ゆめあるチャンネル
保育士の膝に子どもを座らせて絵本を読むのもいいですね。
機嫌がよくなると「あー」「うー」と、よく声を出すようになるので、繰り返し一緒に楽しみましょう。
風船遊び
ふわふわと揺れ、不規則な動きをする風船は、0歳児にとって興味津々のおもちゃです。風船の感触を楽しむ、つかむ、集める、ハイハイで追いかける、運ぶなど、工夫次第で遊び方も豊富。
風船に動物などの絵を描いて楽しめそうですね。風船遊びは、子どもの好奇心や脳を刺激する遊びに一役買ってくれます。
1歳児
ひとりで歩けるようになったり、簡単な言葉を話せるようになったりと、成長が大きい1歳児の時期。
自我が芽生え始めトラブルになることもありますが、人と関わりながらコミュニケーションの取り方を学ぶなどがねらいとなってきます。
- 手先の細かい動きができるようになる
- 友達や保育士とのコミュニケーションの取り方を知る
- 順番を守るなど簡単な遊びのルールを知る
- 新しい言葉を吸収し、発語を楽しむ
1歳児におすすめの室内遊びを紹介します。
新聞やぶり
身近にある新聞紙も、遊びのおもちゃに最適です。新聞をビリビリ破る・丸める・ちぎることで、指先を動かすトレーニングになります。
また、簡単な道具(マント)が作れたり、小さくなった新聞紙を紙吹雪のように降らせたりと、多彩な遊び方で楽しめるのも特徴。
遊んだあとの「お片付け」も、楽しめる遊びへと誘えます。
「みんなで集めよう」など声かけを工夫しながら、お片付けも楽しくしていきましょう。
シール貼り
子どもに人気のシール貼り。
一見簡単そうに見えるシール貼りも、1歳児にとっては難しい遊びです。片方の手でシートを持ち、反対の手でシールをはがす行為だけでも、手首や指先の使い方の練習になっています。
はがれたシールを狙ったところに貼るのもまた、大きなトレーニング。指先が器用になると、脳への刺激にもつながります。
さまざまな柄や色、大きさのシールを用意して子どもが自分で選んで楽しめるようにしましょう。
手遊び
0歳児では見ていることが多かった手遊びも、1歳児になると動きを真似して楽しむようになります。
*くいしんぼうゴリラ|保育士バンク!公式YouTube
*さかながはねて|保育士バンク!公式YouTube
*バスごっこ|保育士バンク!公式YouTube
身体を動かすことで脳の発達にも良く、リズム感も身についていきます。
また、言葉を覚えるきっかけになる場合も。
「もう1回」とリクエストされることもあるでしょう。
リクエストされるということは、子どもたちが気に入ったということです。
一緒に繰り返しながら楽しみましょう。
2歳児
2歳児は、生活面において自分でできることが増え「自分でやりたい」思いが高まる時期です。遊びにおいても、友達との関わりが増え、簡単なルールのある遊びもできるようになっていきます。
次のようなねらいを考えてみましょう。
- 簡単なルールのある遊びを楽しむ
- 友達と遊ぶ楽しさを知る
- 会話や集団遊びを通してコミュニケーション能力を養う
2歳児におすすめの室内遊びを紹介します。
だるまさんがころんだ
【遊び方】
- 鬼を1人決め、基点となる場所(壁や木)に立ち、鬼以外は反対側に並ぶ
- 鬼は他の子どもに背を向け「だるまさんがころんだ」と唱える
その間他の子どもは鬼に向かって近づく - 鬼は「だるまさんがころんだ」と唱え終わったら振り向き、動いている人がいたら指名
指名された人は鬼の横に並ぶ - 2~3を繰り返す。最後まで残っている子どもは、鬼に近づき「切った」と背中にタッチ
- 「切った」の合図で鬼以外の子どもは一斉に鬼の反対側に逃げる
- 鬼が「ストップ」というと全員がその場で止まる
- 鬼は、そこから3歩以内の移動で1番近い子どもにタッチ
タッチされた子どもが次の鬼になる
中には、瞬時に止まることが難しい子どもや、ルールを理解しきれていない子どももいるため、みんなが楽しく遊べるよう考慮しておきましょう。
全員が逃げる際には衝突などの事故にならないよう注意が必要です。
しっぽ取りゲーム
しっぽになるものを人数分用意しておきましょう。
バンダナなどの柔らかくしっぽにつけやすいものがいいですね。
【遊び方】
- ズボンのお尻側に用意したしっぽの先を入れる
- ゲームの時間・走り回る範囲などを決める
- 「よーい、どん」の合図で自分のしっぽを取られないようにしながら、他の子どものしっぽを取る
- しっぽを取られたら、走る範囲の外に出る
- 時間内に残っていた人全員が勝ち。場合によって、最後の1人になるまで行うこともある
約束事やルールはしっかり最初に伝え、みんなが守りながら楽しく遊べるようにすることが重要です。
また、走るので友達とぶつかる可能性もあります。怪我には注意しましょう。
簡単な絵合わせ
2歳児では、絵合わせカードもできるようになります。絵合わせカードは、2枚で1組になっているため、1枚ずつ机に並べ、相方のカードを見つける遊びです。
絵を合わせて楽しんだり「カードを多く見つけた人が勝ち」とルールを決めても楽しめます。
トラブルを避けるため、子どもが遊び方を理解するまで、保育士が仲立ちするといいでしょう。オリジナルの手作りの絵合わせカードを制作しても楽しめそうですね。
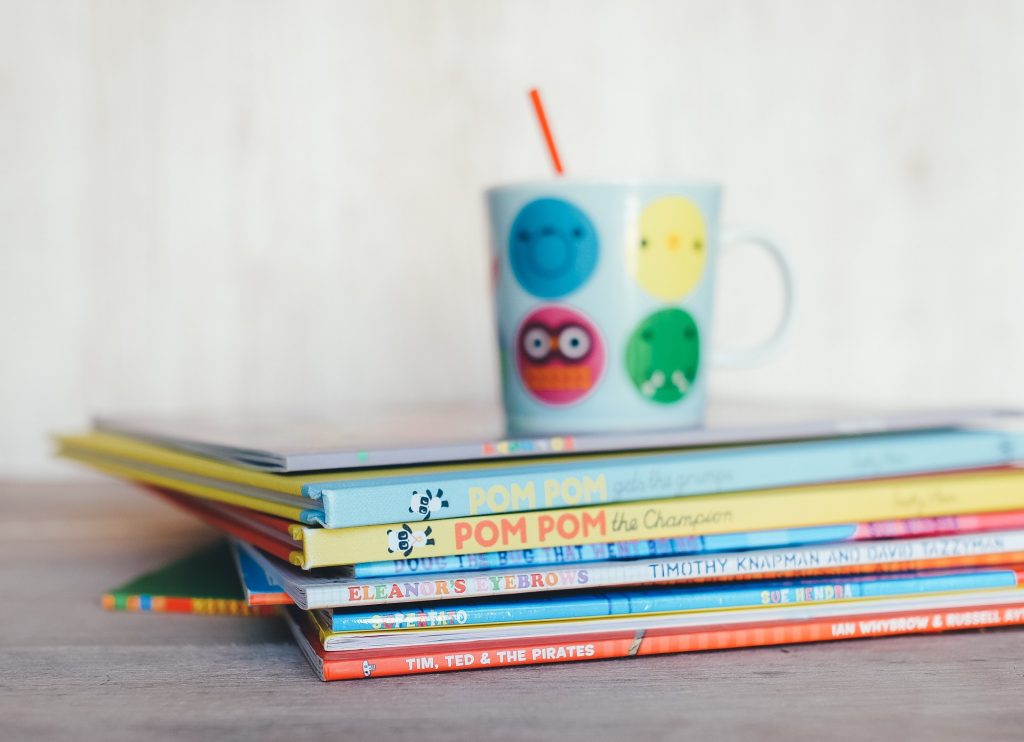
保育でおすすめの室内遊び【幼児向け】
幼児期になると、友達と一緒に遊ぶことを楽しみ、イメージを共有できるようになるため、室内遊びも集団で遊ぶものが増えていきます。
幼児期におすすめの室内遊びを年齢別にみていきましょう。
3歳児
身の回りのことがある程度できるようになり「いやいや期」も過ぎる3歳児の時期。
言葉も急に増え、感情を伝えられるようになるので、友達と集団遊びも増えてきます。
3歳児のねらいは、次のようなものが挙げられます。
- 友達と同じ場所で遊ぶ楽しさを味わう
- ルールを覚え、少しずつ社会性を身につけていく
ルールを守りながら、友達と関われるような遊びを提供するといいですね。
フルーツバスケット
人数より1つ少ない数の椅子を用意します。
【遊び方】
- 椅子を内側に向け、円になるように並べる
- 子どもたち全員にフルーツを割り当てる
- 真ん中に立つ人を1人決め、その人以外は椅子に座る
- 真ん中の人は、割り当てられたフルーツの中から好きなフルーツの名を言う。該当したフルーツの子どもたちは、席を立ち他の椅子に座る。この際、真ん中だった人も席取りに参加する
- 席に座れなかった1人が真ん中に立ち、同じようにフルーツを言う
- 4~5を繰り返す中、真ん中の人が「フルーツバスケット」といった際には、全員が席を移動しなければならない
椅子の脚に引っかかるなどの転倒に気をつけながら楽しみましょう。
フルーツではなく、色や形にしても盛り上がりそうですね。
ジャンケン列車
ジャンケンをしながら列車をつくり、最後1本の列車になったら終了するゲームです。
【遊び方】
- 1対1でじゃんけんをして、負けた人が勝った人の肩に手を置き、列になる
- 先頭にいる人同士でじゃんけんをして、負けた先頭の人が勝った人の列の最後につながる
- 最終的に1本の列車になるまで繰り返す
じゃんけんの勝ち負けを理解していない子どもも予想されるので、できるだけ保育士が仲立ちしながら行いましょう。
4歳児
4歳児は運動機能が大きく発達し、スキップなどの高度な動きもできるようになります。
ねらいには、保育士や友達との集団遊びに親しみを持ちながら、自分の好きな遊びをみつけることが挙げられます。
好奇心も旺盛な時期なので、想像したり考えたりできるよう誘っていきましょう。
4歳児向けの室内遊びを紹介します。
リトミック遊び
リトミックとは、音楽に合わせて身体を動かす音楽教育法のひとつです。音楽に合わせて動物になったり、動きをとめたりし、体全体を使って遊びます。同じ動きを真似するのではなく、自由な感性を表現して楽しむものなので正解がありません。
たとえば、「ゾウ」になりきるのがお題だとすると、
- 水浴びをする仕草
- 鼻を揺らして歩く仕草
- ノッシノッシとゆっくり歩く仕草
どれを表現しても自由です。
感性が養われるので、カリキュラムとして取り入れている保育園もあります。
粘土遊び
粘土遊びは、子どもの自由な想像力が発揮される遊びのひとつです。粘土の種類は、小麦粉粘土や紙粘土、油粘土などさまざまあり、それぞれ特長が異なります。
たとえば、小麦粉粘土は、小麦粉から作られているので食べても安心です。紙粘土は軽く、臭いもないので扱いやすいですが、乾きやすいのが難点。造形には、定番の油粘土が向いています。
粘土遊びで作るテーマや展開に沿って、合う粘土を選んでみてもいいかもしれませんね。
子どもが想像力を引き出せるように工夫していきましょう。
椅子取りゲーム
王道の椅子取りゲームは、子どもにも人気があります。明るい音楽をかけたり、テンポを変えたりとバリエーションも豊富です。
優勝した子どもには手作りメダルを授与、インタビューをするなど一味違った楽しみ方もできますね。転倒に注意しながら楽しみましょう。
5歳児
知力・体力ともに発達し、複雑なこともできるようになる5歳児。年長児の自覚を持つ5歳児のねらいには、遊びの中で自分の役割を見つけ、一人ひとりの力を発揮するなどが挙げられます。5歳児向きの室内遊びを紹介します。
転がしドッジボール
ルールはドッジボールと同様です。ただし、ボールを投げるのではなく転がして行います。
【遊び方】
- 2つのチームに分ける
- 子どもが動ける範囲と中央のライン、ボールが当たった子どもが集まる範囲を決める
- 保育士の合図でスタートし、ラインからはみ出さないよう相手に向かってボールを転がす。
- ボールに当たった子どもは終了となり、外野へ
- 最後まで子どもが残っていたチームの勝ち
その他、内野と外野に分かれて行う遊び方もあります。
この場合は、外野から相手チームにボールを当てることができると内野に復活できます。
時間や場所の広さなども考慮して行いましょう。
マットを使った運動遊び
転がる・押す・歩く・跳ぶなど思いきり身体を動かせるマット運動は、保育園でもよく取り入れられています。
コロコロ転がったり、前転をしたり…のびのびと動けるよう、大きめのマットを用意しておくと良いでしょう。
また、捻挫などにならないよう、準備運動はしっかり行うことが重要です。
カードゲーム
神経衰弱や絵合わせ、パズルなどの高度なゲームもできるようになります。勝ち負けで、ときに感情がぶつかることもありますが、友達同士での関わりも大切なことです。
すぐに仲介に入るのではなく、まずは子どもだけで解決できるよう見守りましょう。見守ることで、子ども自身の心の成長につながります。
エスカレートしてケンカになりそうな時、手がでてしまいそうな時には、間に入って双方の意見を聞き援助しましょう。
まとめ
どの年齢の保育においても、室内遊びは重要な遊びのひとつです。室内遊びを行う際は、発達のねらいを踏まえたうえで楽しめるよう工夫していきましょう。
梅雨時期や寒い時期などは、室内での時間が多くなりストレスがたまりがちですが、体を動かす室内遊びも適度に取り入れ、楽しく過ごしたいものですね。