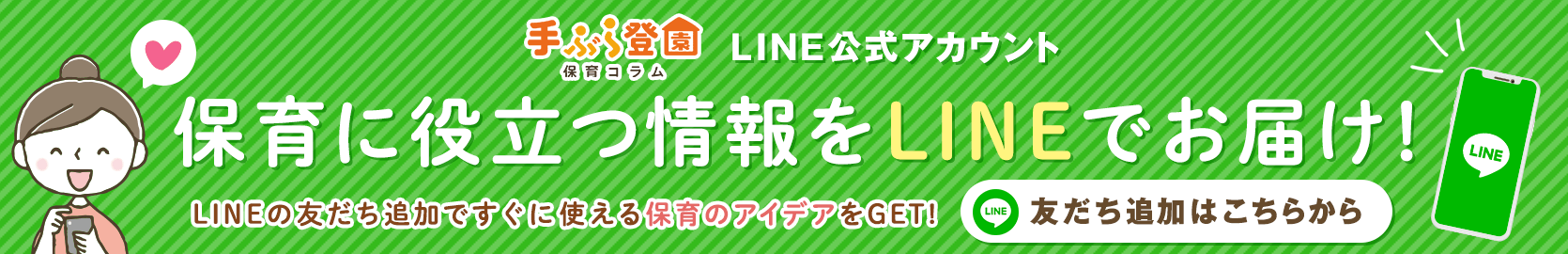保育士の配置基準とは?計算方法や配置基準改善への動きについて

クラス担任の保育士の人数は、配置基準によって決められています。
たとえば、0歳児15人クラスの場合、保育士は最低5人必要です。
70年以上変わらない基準に対して改善を求める声は強く、2023年3月には保育士などで作る団体が国に対して改善を求める要望書が提出しました。
今回は、保育園を運営するにあたり欠かせない保育士の配置基準について、詳しく解説していきます。
保育士の配置基準とは
保育士の配置基準とは、保育士1人あたりで何人の子どもを保育できるか、を示した基準です。
配置基準は厚生労働省の「児童福祉施設最低基準」によって定められており、保育園を運営するにあたり守らなければなりません。
配置基準では「保育士を常時2名以上配置すること」も原則となっているため、たとえ子どもが1人の場合でも、保育士は1人で保育を行うことはできません。
| 0歳児 | 保育士1人に対して子ども3人 |
| 1、2歳児 | 保育士1人に対して子ども6人 |
| 3歳児 | 保育士1人に対して子ども20人 |
| 4歳以上児 | 保育士1人に対して子ども30人 |
基本的には国で定めた基準に従って保育士を配置しますが、自治体や施設によって基準が異なる場合もあります。
保育施設別の配置基準
ここでは、認可外保育園と地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)の施設についてそれぞれ解説していきます。
認可外保育園
認可外保育園とは、国の認可基準は満たしていないものの、各都道府県の基準は満たし知事からの認可を受けている施設です。
配置基準においても、認可保育園に比べて緩やかに設定されています。
内閣府「認可外保育施設の質の確保・向上について」で定められている基準は、以下の通り。
| 11時間以内の保育の場合 | 児童福祉施設最低基準に規定する数以上 |
| 11時間を超える保育の場合 | 現に保育されている児童が1人の場合を除いて、常時2人以上 |
また、職員の3分の1以上は保育士または看護師の資格が必要となります。
地域型保育事業
小規模保育【A型:定員6~19名以下】
A型とは、保育所分園やミニ保育園に近い形態の保育です。
配置基準は次の通り。
| A型 | 定員6~19名以下 | 保育所の配置基準+1名 | 全員が保育士※ |
| B型 | 定員6~19名以下 | 保育所の配置基準+1名 | 1/2以上が保育士※ |
| C型 | 定員6~10名以下 | 3人につき1人 (補助者を置く場合は、5人につき2人) | 家庭的保育者 |
※保健師、看護師又は准看護師の特例を設けています
家庭的保育事業【定員5名以下】
家庭的保育事業とは、自宅や他の場所で少人数の子どもに保育を行うことです。
配置基準は、小規模保育C型と同様の基準が定められていますが、定員は5人以下なので間違わないようにしましょう。
| 定員5名以下 | 3人につき1人 (補助者を置く場合は、5人につき2人) | 家庭的保育者 |
事業所内保育事業
事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する施設です。
配置基準は、子どもが20人以上なら国が定めた基準と同様に、子どもが19人以下なら小規模保育A型・B型と同様となります。
| 定員19人以下 | 小規模保育A型・B型の基準と同様 |
| 定員20人以上 | 保育所の基準と同様 |
保育士の配置基準の計算方法
保育施設の配置人数は、下記の計算方法で出すことができます。
子どもの人数÷配置基準の定員数=保育士の数
この計算方法をもとに、計算の流れを紹介します。
各クラスの定員人数を決める
配置基準を計算する際、各クラスの定員人数は重要になります。
定員人数を想定していきましょう。
今回は、以下のように仮定してみます。
- 0歳児…9人
- 1歳児…12人
- 2歳児…18人
- 3歳児…20人
- 4歳児…30人
- 5歳児…30人
定員119名の認可保育園を設定します。
定員を設定基準で割る
上記で想定した定員を基準で割り、必要な保育士の人数を算出していきましょう。
ここでは、国が定めた配置基準をもとに計算します。
(小数点以下が発生した際は、小数点以下を四捨五入して計算)
- 0歳児9人÷3=保育士3人
- 1歳児12人÷6=保育士2人
- 2歳児18人÷6=保育士3人
- 3歳児20人÷20=保育士1人
- 4歳児30人÷30=保育士1人
- 5歳児30人÷30=保育士1人
計算により、各クラスに必要な保育士の人数や定員119名の園全体では、最低11人の保育士が必要だとわかります。
延長保育などに必要な保育士の人数を加算する
計算結果で出た「最低11人の保育士」は、あくまでも日中に必要な保育士の人数です。
したがって早朝・夕方の延長保育時なども考慮しなければなりません。加えて、保育園に子どもがいる時間には常に2人以上の保育士が必要という原則があります。
これらを踏まえると、実際に11人の保育士でシフトをまわすことは困難です。人数を計算する際には、日中の保育士+朝・夕に必要な保育士の人数も加算し、多めの保育士を確保しておくようにしましょう。
保育士の配置基準は緩和してきている
これまで配置基準は昭和23年に定められて以来、70年間変わらずに進められてきました。
しかし、待機児童問題の解消を目指すため、平成28年4月から緊急的な対応として基準が緩和されました。
保育所等における保育士配置に係る特例 【平成28年4月から実施】
※②③の特例適用に当たっては、全体で1/3を超えない(保育士を2/3以上配置する)ことが必要となります
①朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例
保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。
※子育て支援員は、自治体の研修を修了することで認定を受けることができます。
②幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例
保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて活用可能とする。
※幼稚園教諭は3歳児以上・小学校教諭は5歳児を中心に保育することが望ましいといった条件があり、保育を行う上で必要な研修(子育て支援員研修など)の受講が求められます。
③保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例
保育所等を8時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる保育士数(例えば15名)を上回って必要となる保育士数(例えば15名に追加する3名)について、子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。
※①における要件に加え、保育士資格取得を促していく
保育士の配置基準改善に向けた動き
「次元の異なる少子化対策」に向けて様々な保育サービスの充実が検討される中、保育現場では配置基準の見直しや保育士の待遇改善を求める声が上がっています。
保育ICTのコドモンが実施した配置基準に関するのアンケートでは、80%の施設が「配置基準の改善は不適切保育の減少に寄与する」という結果が出ました。
【調査レポート】保育士の配置基準問題 80%が「配置基準の改善は不適切保育の減少に寄与」と回答
この結果からも分かるように、子どもの安心・安全・健やかな育ちのために質の良い保育の確保を目指すためにも、まずは保育士の負担改善が重要だと考えられます。
冒頭に紹介した要望書の提出をきっかけに、配置基準の改善が実現することを期待したいですね。