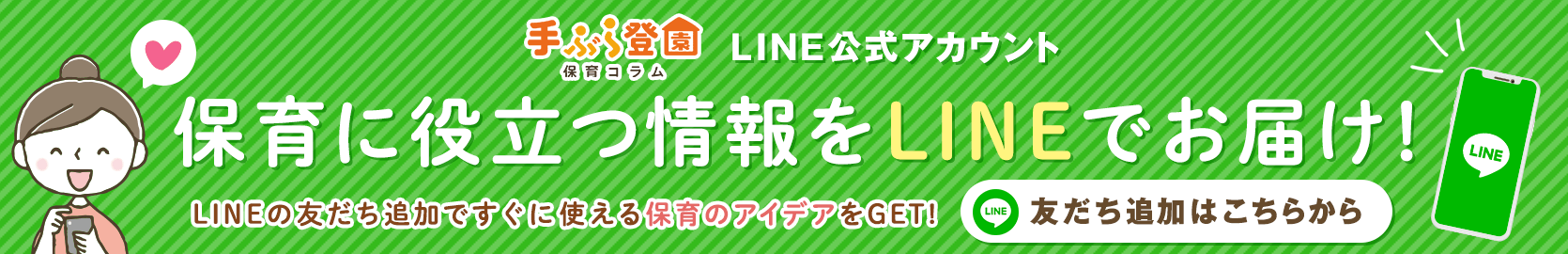町長が語る「おむつの定額制サービス」導入の背景~三宅町の「顔の見える」子育て支援とは~
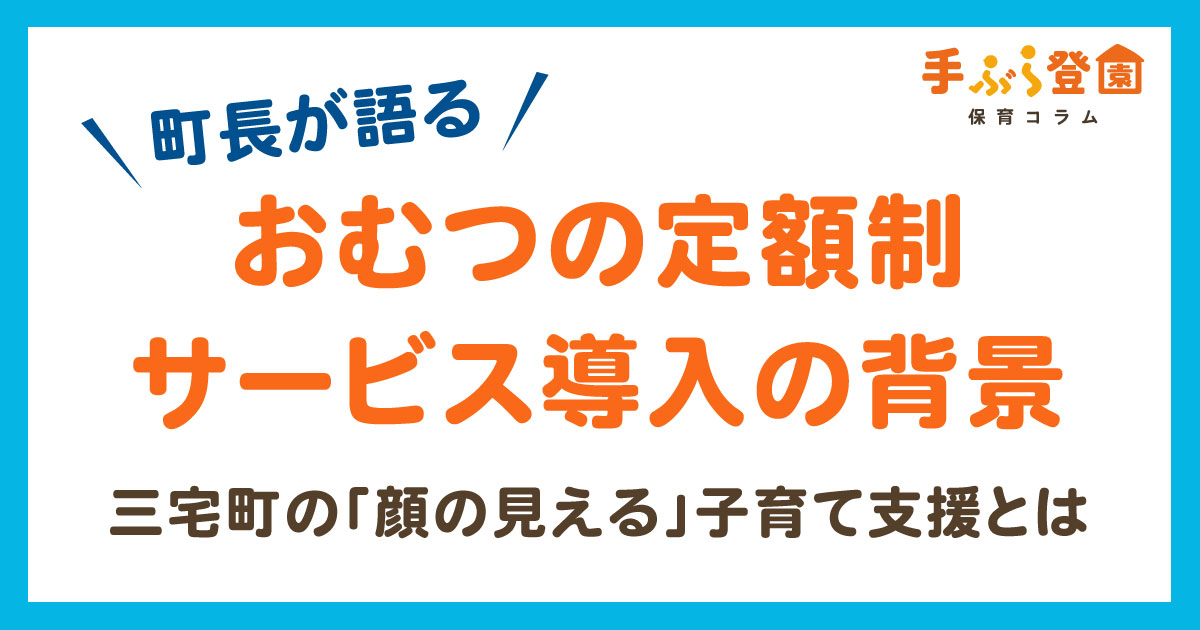
日本で2番目に小さい町、奈良県三宅町。子育て支援に力を入れるなかで、2020年7月からおむつの定額制サービス『手ぶら登園』を採用しています。
以前の記事では、認定子ども園「三宅幼児園」さんに、導入前後の変化などを伺いました。
この取り組みを最初に提案したのは、実は三宅町長の森田浩司さん。年度の途中ながら、思い切った切り替えができた理由はどこにあったのでしょうか。
同町の子育て支援の考え方、そして『手ぶら登園』導入の背景を、森田さんと健康子ども局・局長の植村恵美さんに聞いていきます。
地元のみんなで、支え合って子育てを
——三宅町ではこれまでも、子育て支援に長く力を入れておられたと伺いました。
森田:小さな町のなかで、「顔の見える関係」を大事にしながら支援を重ねていました。出生前からすべての家庭に保健師さん、助産師さんなどが訪問して、一人ひとりの事情や悩みにも丁寧に寄り添うよう心がけています。
そのため、職員の名前や顔をみなさんずっと覚えてくださってるんです。スーパーなどで会っても気軽に話し合う光景が、日常的に見られていますね。
植村:地元のみんなで、支え合って子育てをしていこうと考えています。発達に特徴をもつお子さんの場合も、できるだけ園や学校、学童保育で過ごせるようにするなど、さまざまな連携をしていますね。
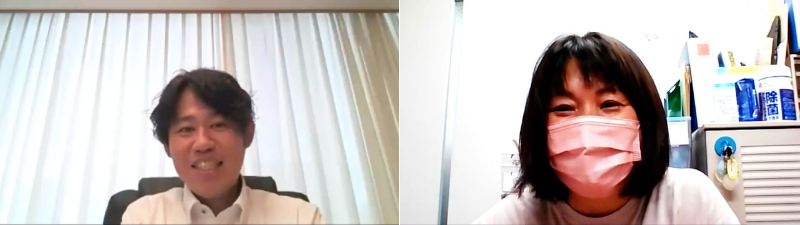
奈良県三宅町町長の 森田浩司さん(左)健康子ども局・局長の植村恵美さん(右)。オンラインでお話を伺いました
——官民の連携も積極的に進められています。どういった狙いがあるのでしょうか?
森田:民間企業の知恵やサービスをお借りすることで、それまで解決できなかった問題や、リソースが足りなくてできなかったことに取り組める可能性があるからです。子育て支援も、行政だけですべてをやろうとするのではなく、どうすればみなさんの負担を軽減できるかを一緒に考えていければと思っています。
手ぶら登園が「園のスタンダードだったら」
——おむつの定額制サービス『手ぶら登園』導入のきっかけは、何だったのでしょうか?
植村:私は、町長から「こういうサービスがあるらしい。どうかな?」と相談を受けたのが最初でした。
森田:さまざまな自治体で官民連携を推進している方から、『手ぶら登園』を立ち上げた上野公嗣さんを直接紹介いただいたんです。三宅町が子育て施策に積極的なことを知ってくれていて、「話を聞くだけでも参考になるのでは」と声をかけてくださいました。
——実際に話を聞かれてみて、どう思われましたか?
森田:まずは「何でこれが園のスタンダードじゃないんだろう」と率直に感じました。私自身も子育てを始めた頃、新生児ってこんなにおむつを換えないといけないんだ、すごい量のおむつがいるんだって体感していたので、それを毎日持っていくなんて本当に大変だと、現状を知って驚きましたね。
しかも1枚ずつ名前まで書かないといけないと聞いて、いやいや、そんなことしてられないぞと。だから内容や目指す世界観を伺って、「すぐに導入したい」と植村局長のところに行ったんです。
植村:正直に言えば、最初は「サブスク」という考え方にピンとこなかったんです。ただ詳しく聞いて、定額かつ使い放題はとてもいいなと思いました。
対象となる子育て世代は、サブスクリプション(定額)で何かを利用することにも慣れてきています。何より日々の負担を直接解決してくれるので、保護者にとってすごく魅力的なのではと感じました。
「だめなら止めよう」から業務改善へ
——料金も町が全額負担する形で、昨年の7月に利用が始まったと聞きました。予算の確保はどのようにされたのでしょうか?
森田:今回、導入を進める要因の一つになったのが、実はコロナ禍の到来でした。そこで感染対策として国から設けられた臨時交付金を、『手ぶら登園』にも使えるとわかったんです。
保育施設に直接おむつが届くこのサービスを使えば、家庭から園への持ち込まれるものを減らすことができる。何が感染経路となるかよくわからないなかで、できる対策はしようと思ったんです。
同時に、「使用済み紙おむつ」を保護者が持ち帰っていた問題も見直し、園内廃棄することも決定しました。
(1記事目:公立園が「おむつの持ち帰り」を止めた理由。“慣習”を疑う三宅町の実践)
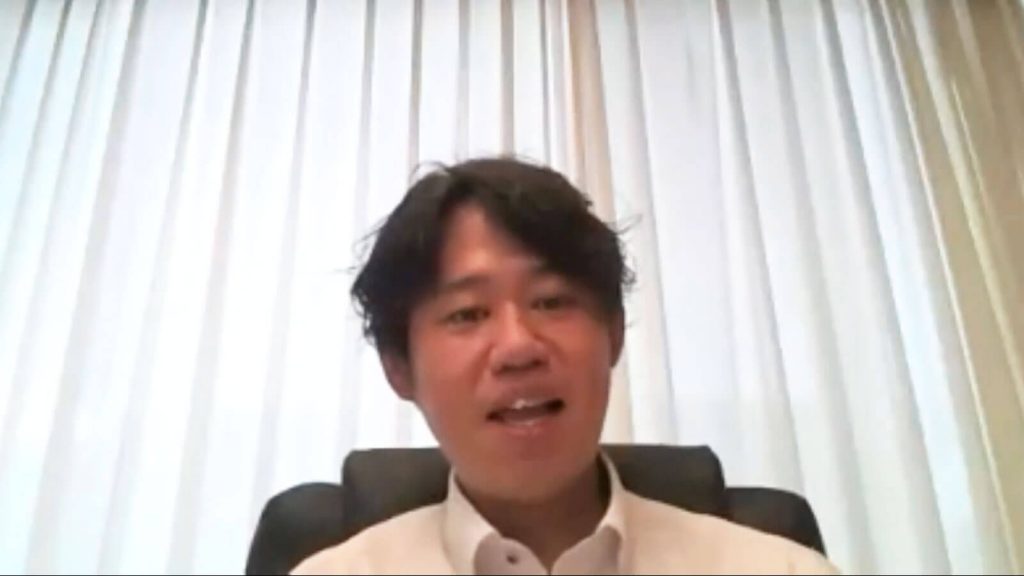
——園側から、事前に不安の声などはありませんでしたか?
植村:園長が現場で働く職員に、メリットをきちんと説明してくれたんだと思います。保護者にとってすごくいいものですし、保育者の管理も楽になる可能性がある。
「まずは一回やってみよう」と職員に話してくれた、と聞いています。
森田:おむつの廃棄と同様に、まずは単年度でチャレンジしながら、「だめだったら止めよう」という選択肢も用意していました。結果それがよかったのかなと感じています。

定員146名の、幼保連携型認定こども園「三宅幼児園」。公立園で初めて『手ぶら登園』を導入。利用料金は三宅町がすべて負担し、保護者は無料でサービスを受けることができる。
——実際に導入されて以降、保護者・保育者どちらにとっても「負担が減った」という話は、以前の園への取材でもお聞きしています。
植村:おむつに書かれた名前を1枚ずつ間違えないように確認して、使い終わったものも1つずつ名前とごみ箱をチェックして……といった作業がなくなり、業務面でも気持ちの面でも「すごく楽になった」と言ってくれています。
また、残り枚数を気にせず使える点も好評です。ちょっとでも汚れたらすぐに交換できるので、子どもたちの衛生面にもよかったのかなと感じていますね。
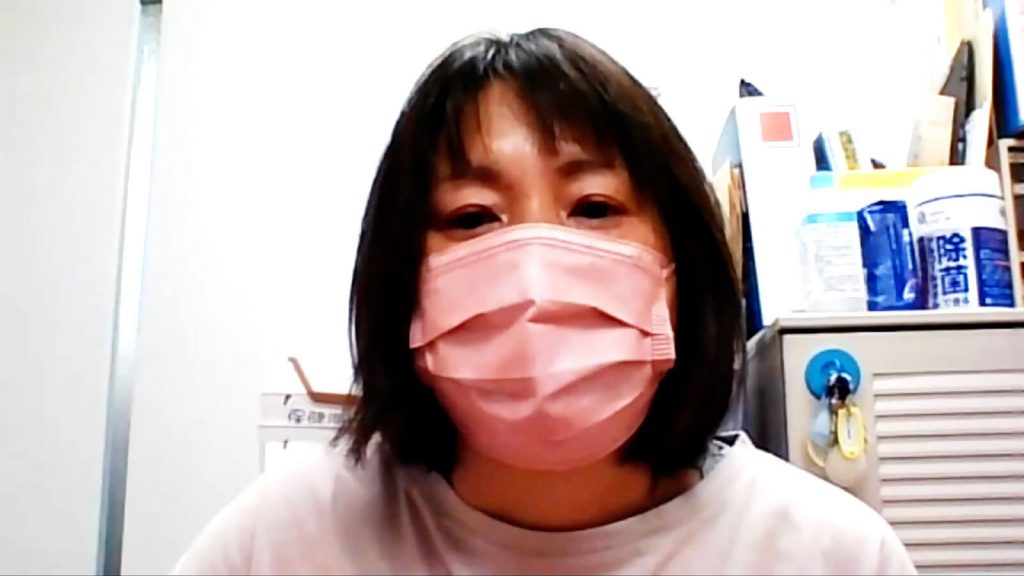
社会課題を解決していく、新しい官民連携の形
——『手ぶら登園』を利用した保護者の反応はいかがでしたか?
植村:導入後しばらくしてからアンケートを取ると、利用している保護者全員が喜んでくれていることがわかりました。朝のバタバタが、かなり減ったという声も聞きますね。
森田:どれだけの保護者が助かったか。改めて考えても、導入して本当によかったと思います。
——臨時交付金を活用してのスタートでしたが、今後も続けられると考えていいのでしょうか?
植村:満足度も高いので、元に戻したらみなさんに怒られてしまいますね。
森田:それはもう、私たちが頑張らないといけないところです。今後もしっかり続けていく必要があると感じています。
——こうした官民連携の事例が、今後も増えていけばと思います。
森田:今回の取り組みで、「民間サービスの活用によって、住民のみなさんの課題を解決する」という成功体験が積めた。行政職員にとっては、それも非常によかった点です。
自分たちだけですべてやるのではなく、いいものをどう取り入れるかという発想ができるようになった。次の挑戦にまたつながっていく、一つの理想的な官民連携の形だったのかなと感じています。
取材後記
「子どもの最善の利益」が何より大切になる児童福祉の世界。ただ、それを実現するために、福祉で働く職員さん、取り巻く保護者さんなどを支える「サービス」が貢献できる場面も、まだまだあるはずです。
行政として改めてそこを問い直した三宅町の実践は、全国の自治体や福祉施設にとって、一つの大きなヒントになるのではないでしょうか。
手ぶら登園導入を支援する実証実験プログラムはこちら
自治体向け資料をダウンロード