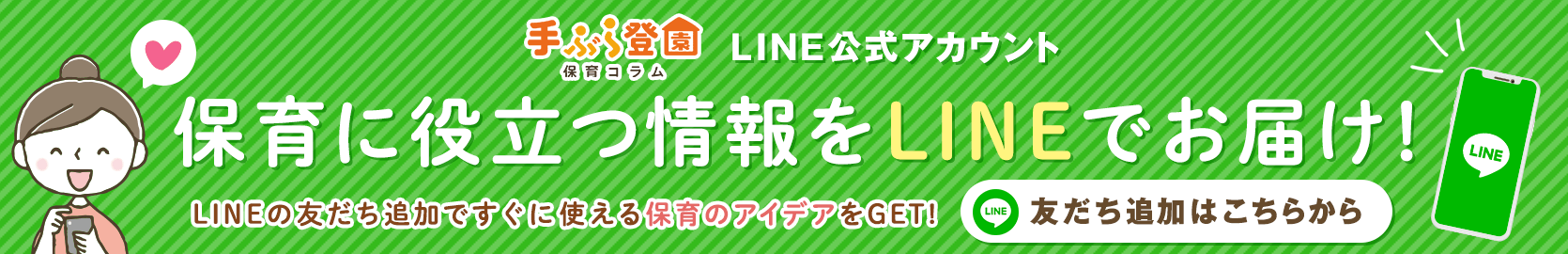保育園で楽しくお面を作ろう!お面の作り方と種類をご紹介!

「保育園でお面を作って遊びたいけれど、どうやって作ればいいの?」「どんなお面の種類があるんだろう?」と悩むことがありますよね。
お面はパーツが複数に分かれているため、年齢によってすべて作るか、一部だけ作るかを決めることができます。メインの顔の部分は、色の塗り方やデザインに子どもたちの個性が出てくるので面白いですよ!
今回は、保育園での遊びの1つとして、お面の作り方をご紹介します。お面と言うと節分の鬼のイメージが強いですが、行事だけでなくごっこ遊びにも使えるので、ぜひ参考にしてください。
保育園でお面を作るために用意するもの
「さっそくお面を作ろう!」と思っても、何を用意すれば良いかわからないことがありますよね。そこで最初に、お面を作るための材料についてご紹介します。お面を作るために必要な材料は、以下のとおりです。
- 画用紙
- ハサミ
- 輪ゴム
- ホッチキス
- 色鉛筆やクレヨン
- セロハンテープ
- シール
必要に応じて、毛糸やトイレットペーパーの芯なども用意します。ハサミやホッチキスなど、取り扱いに注意が必要な道具も含まれているので、保育中は子どもたちから目を離さないようにしてください。
お面を作る材料は、比較的安価で揃えることができ、余った分は他の製作にも使い回せるものばかりです。上手に材料を使い回し、経費削減にもつなげていきましょう。
お面作りのために保育士が行う事前準備
保育士が行う事前準備の内容は、子どもの年齢により異なります。2歳児など小さい子どもたちの場合は、事前に保育士が以下の2つのパーツを作っておきましょう。
- お面の顔のパーツ
- 輪っか(帯)の部分
ハサミで切る簡単な作業やお面の顔を描く作業は子どもたちに任せましょう。顔を作るときは、クレヨンや色鉛筆で描く以外にも、シールを貼ったり、穴をくり抜いたりして楽しめます。
5歳児は自分で1から作ることができるため、保育士は材料のみ準備します。作っているときに失敗する恐れもあるので、材料は多めに準備しておくと安心です。
また、初めて保育でお面製作をするときは、まず保育士が自分で作ることができるか確認をしなければなりません。子どもたちの前に、保育士に対しての指導も行っていきましょう。
保育園でのお面の作り方
ここからは、お面の詳細な作り方を3つのステップに分けてご紹介します。
①お面の輪っか(帯)を作る
最初に、お面の輪っか(帯)の部分を作ります。頭につけるものなので、すぐに壊れないよう頑丈に作りましょう。
【作り方】
- 画用紙をベルト状に折り畳む(薄いと破れる可能性があるので、分厚めに作る)
- ホッチキスを使ってつなぎ目の部分に輪ゴムをつける
子どもたちの頭の大きさは一人ひとり違うため、輪ゴムで微調整できるようにしてください。あまりにも窮屈すぎる、ぶかぶかすぎる場合は、その子ども専用にさっと作り直すこともできます。
②お面を作る
お面の部分は、画用紙でパーツを作って切り貼りしたり紙に絵を描いて切り抜いたりと、作り方はさまざまです。顔を描くお面もあれば、目と口の部分を切り抜くお面もあります。今回は、顔を描く方法でのお面の作り方を見ていきましょう。
【作り方】
- 表情は色鉛筆やクレヨンを使って、子どもたちの描きたいように描いてもらう
- 必要であれば、シールを自由に貼ってもらう
- 作ったお面をさらに丈夫にしたい場合は、ラミネート加工をする
お面の部分には、子どもたちの個性がよく出ます。子どもたちが作ったもの、描いたものは否定せず、たくさん褒めてあげましょう。
③輪っかとお面をくっつける
それぞれのパーツができたら、輪っか(帯)とお面をくっつける作業を行います。くっつける位置がずれると前が見えなくなるので、あらかじめ印をつけるか、保育士が補助に入ってください。
【作り方】
- お面を机に置き、その上に輪っか(帯)を置いてホッチキスで固定する
- 頭にはめてみて、ぐらぐらしないか、輪っかとお面がしっかりつながっているかを確認する
お面をつけたとき、つなぎ目部分に髪の毛が絡まる可能性があります。髪の毛が絡まないためにも、ホッチキスをとめる向きには気をつけましょう。
保育園で作れるお面の種類
お面と言えば、「節分」を思い出す人も多いのではないでしょうか。しかし、節分で使うものの他にも、お面の種類はたくさんあります。いろいろな生き物やキャラクターになりきって、ごっこ遊びを楽しむのも良いでしょう。
鬼のお面
2月の節分に必要不可欠な鬼のお面です。お面作りをとおして、そもそも節分とはどんな行事なのか、鬼の役割や豆をまく意味などを学ぶことができます。
赤鬼、青鬼、黄鬼など好きな色のお面を作れるので、カラフルで可愛いお面がたくさんできて面白いです。鬼=怖いというイメージがありますが、自分たちで作った鬼のお面には子どもたちも愛着を持てるでしょう。
それぞれの鬼のオリジナル性を出したいときには、顔の表情や色だけでなく、毛糸を使って髪の毛を付け足したり、つのの本数を変えてみたりして工夫できます。
キャラクターのお面
いつもお家のテレビで見ているキャラクターのお面は、子どもたちが大喜びすること間違いなしです。
特に、子どもたちが大好きなアンパンマンのアニメに出てくるキャラクターは、シンプルで製作しやすくなっています。土台は丸や四角が多いため、準備もしやすいでしょう。
アンパンマン以外に、NHK教育テレビのキャラクターや、他のアニメキャラクターのお面も作ることができます。大好きなキャラクターなのでテンションも上がり、製作にも真剣に取り組めるでしょう。
お面を作った後は、キャラクターになりきってごっこ遊びができます。製作で細かい作業をした後は、思いきり体を動かして遊ばせてあげましょう。
動物のお面
うさぎやねこ、くまなど童謡や絵本に出てくる動物もお面にしやすいです。お面をつけた子どもたちが絵本の内容にしたがって動くことで、物語を飽きずに楽しめるでしょう。
子どもたちは動物になりきっているので、動きや声もまねして遊べます。
動物を題材にした歌や絵本はたくさんあります。歌に合わせて踊ったり、跳ねたりできるので、次の活動にもつなげやすくなるでしょう。
ぴょんと跳ねるうさぎやよちよち歩きのペンギンなど、動作が激しくない動物を選ぶのもポイントです。
ハロウィンのお面
ハロウィンの時期は、お面を作って仮装パーティーを楽しめます。魔女やドラキュラ、かぼちゃ、おばけなどが登場し、子どもたちは非日常空間を味わえるでしょう。
さらに、「トリック・オア・トリート」のセリフでお菓子やそれに代わるものをあげることで、いつもよりはしゃいで楽しんでくれます。
ハロウィンには特にキャラクターの縛りはないため、可愛いお姫様やかっこいい恐竜など、子どもたち独自のアイデアも生まれるかもしれません。年に一度の行事なので、張り切って参加してくれるでしょう。
まとめ
今回は、保育園でできるお面の作り方をご紹介しました。お面作りは実はとても簡単で、新人保育士でも指導しやすい内容になっています。製作のハードルは低めなので、ぜひお面作りに挑戦して、次の活動にもつなげてみてください。
また保育園の経営者は、常に現場のことで忙しい保育士に、少しでも有益な情報を伝えることが大切です。なるべく準備に手間がかからないよう工夫して、保育士に遊びのアイデアを提案しましょう。