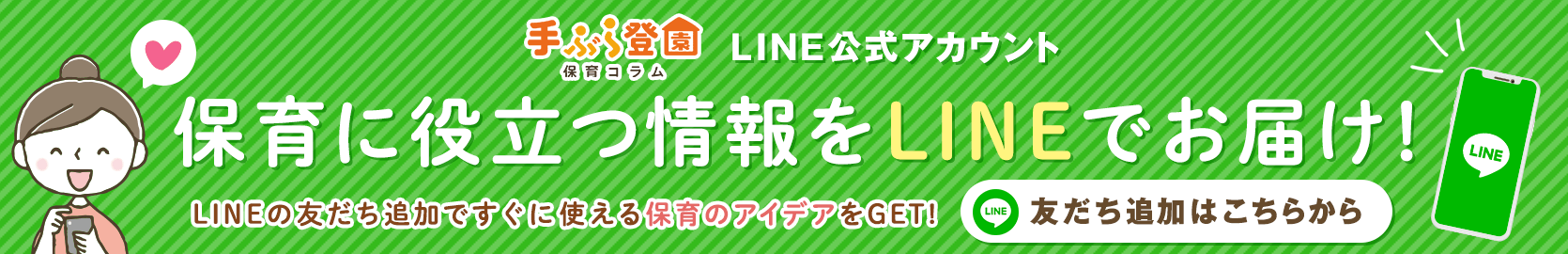保育に欠かせない五領域とは?ねらいや内容も解説

保育士が指導案を書くにあたって、重要になるのが「五領域」です。
言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、五領域を意識することで日々の保育にも役立つでしょう。
今回は、五領域の内容やねらいについて解説していきます。
保育における「五領域」とは?

五領域とは「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域を指します。
| 健康 | 心と体の健康を維持する領域 |
| 人間関係 | 周囲の人とのコミュニケーション力を育てる領域 |
| 環境 | 身近な環境とのかかわりに関する領域 |
| 言葉 | 言葉の獲得に関する領域 |
| 表現 | 思いや感じたことを表現する領域 |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
保育所保育指針にも記載されており、保育園では、この五領域に基づいて指導案の作成や日々の保育が行われています。
上記5つの領域は、どれか1つに集中して教育されるものではありません。
すべて総合的に組み合わせながら、子どもの心身の発達をサポートしています。
保育の五領域の内容とねらい

五領域は、子どもが小学生になるまでに育てておきたい基礎の力を表したものであり、重要です。
五領域について、それぞれの内容とねらいを見ていきましょう。
健康
健康の領域では、体や健康に関心をもち、心身の機能を高めていくことをねらいとしています。
| ねらい | ・明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう ・自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする ・健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身につける |
| 内容 | ・保育士や友達と関わり、安定感をもって生活する ・食事や午睡、遊びや休息などの健康的な生活リズムを身につける ・さまざまな食品に触れながら保育士や友達と食べることを楽しむ ・衣服の着脱、排泄などを自分でしようとする ・走る、跳ぶ、押す、引っ張るなど全身を使った遊びを楽しむ ・危険な場所、遊び方に注意し、安全に気をつけて行動する |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
たとえば「外から帰ったら、石鹸で手を洗おうね」と手洗いの仕方を知らせたり、子どもが自分で衣服の着脱ができるよう、着脱の仕方を知らせたりするのが、健康の領域に入ります。
子どもたちにもわかるよう、実際にやってみせたりしながら伝えることが重要です。
人間関係
保育士や友達と関わる中で、ルールを守ることや思いやりの心を育てるねらいがあります。
| ねらい | ・園での生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう ・身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感をもつ ・社会生活における望ましい習慣や態度を身につける |
| 内容 | ・保育士や友達と一緒に過ごすことの喜びを味わう ・自分で考え、自分で行動する ・自分でできることは、自分でする ・いろいろな遊びを楽しみながら、物事を最後までやり遂げようとする ・友達と関わる中で、喜びや悲しみ、楽しさを共感したり、相手への思いやりをもつ ・自分の思いを相手に伝え、相手の思っていることに気づく ・高齢者や地域の人々など、自分の生活と関係の深い人に親しみをもつ |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
たとえば「みんなで遊ぼうね」と一緒に触れ合い遊びをしたり、「お友達を叩いたら、痛いよね」と相手の気持ちを代わりに伝えることで、気持ちに気づけるようにします。
コミュニケーション力を育てるため、人間関係は欠かせない領域です。
環境
身近なものや自然と触れ合いながら、感覚を豊かにしていくことがねらいです。
| ねらい | ・身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で、さまざまなことに興味や関心をもつ ・身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり考えたりし、それを生活に取り入れようとする ・身近な事象を見たり考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする |
| 内容 | ・自然に触れて生活し、その大きさや美しさ、不思議さに気づく ・さまざまなものに触れ、物の性質や仕組みに興味・関心をもつ ・四季の変化に気づいたり、身近な自然に興味をもち、取り入れて遊ぶ ・動植物に親しみをもって関わり、いたわったり大切にする ・身近なものや遊具に興味をもち、考えたり試したり工夫しながら遊ぶ ・生活の中で、数や図形、文字などに関心をもつ |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
たとえば「お花、たくさんあるね」と、戸外時に自然に目を向けるような声かけをしたり、「積み木、丸いね」と図形に関心をもたせたりなど、身近な物の数や自然との触れ合いを通して、五感に働きかける領域です。
言葉
言葉に関心をもち表現しようとする、自分の思いを言葉で伝える、人の話を聞くなどの力を養うねらいがあります。
| ねらい | ・自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう ・人の言葉や話をよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう ・日常生活に必要な言葉がわかるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ保育士や友達と心を通わせる |
| 内容 | ・保育士や友達の言葉や話に興味・関心をもち、親しみをもって聞いたり話したりする ・自分の考えたことや感じたこと、欲求を自分なりに言葉で表現する ・生活の中でその場に応じた必要な言葉を使う ・相手にわかるように話す・いろいろな体験を通してイメージを豊かにする ・絵本や物語などに親しみをもち楽しさを味わう |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
言葉の領域も、欠かせない要素です。
「痛かった」と自分の気持ちを言葉で伝えたり「〇〇ちゃんは、どう思う?」と、問いかけたりすることで、子どもは受け答えの中から、言葉で伝えることの大切さを体験しながら育ちます。
表現
感じたことや考えたことを自分なりに表現し、創造性を豊かにする力を養うことがねらいです。
| ねらい | ・いろいろなものに対して、美しさなど豊かな感性をもつ ・感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ ・生活の中でイメージを豊かにし、さまざまな表現を楽しむ |
| 内容 | ・さまざまな音・色・形・手触り・動きなどに気づいたり、感じたりして楽しむ ・生活の中で美しいものや心動かすものに触れ、イメージを豊かにする ・感じたこと、考えたことなどを音や動き、自由にかいたり作ったりして表現する ・いろいろな素材に親しみ、工夫して楽しむ ・歌を歌う、楽器を使う楽しさを味わう ・自分のイメージを動きや言葉で表現したり、演じたりして楽しむ |
参照元:厚生労働省|保育所保育指針解説(平成 30年 2月)
子どもに表現する楽しさを知ってもらう領域です。
粘土遊びや、リズム楽器、発表会の劇なども表現の領域に分類されます。
感じたこと、考えたことを自由に表現することで、想像力や豊かな感性を育てます。
保育五領域の実践例を紹介

実際に保育現場では、どのような指導方法がなされているのでしょうか。
「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」それぞれの実践例を紹介します。
健康
健康の領域では、おもに遊び、衣服の着脱や生活習慣、食育などの要素が含まれています。
- ハイハイをする、ボールを蹴る、ジャンプをするといった身体的発達の援助
- 靴やズボンなどの着脱を自分でしようとする
- いろいろな食材に触れて、味や食に興味をもつ
- 生活リズムを整え、規則正しい生活習慣を作る
- 「清潔」がわかり、鼻水がでると知らせる
- トイレトレーニングを行う
- 危険・注意すべき点を説明し、安全に気をつけるよう知らせる
特に未満児の間は、発達に個人差があることも多いため、保育士側からの働きかけは重要です。
お手本を見せてみる、「〇〇してみようか」と、子どもが興味をもつような言葉をかけるなど、一人ひとりに合った援助を考えていきましょう。
人間関係
人間関係は、子どもの年齢・発達状況によっても大きく異なってきます。
- 乳児の間は、保育士や親との信頼関係を築き、安心感や愛着を知る
- 1~2歳児は、気持ちを代弁してもらいながら、言葉を習得する
- 3歳以上は、子ども同士の関わりを深めていく
1~2歳児のころは、自我が芽生える一方でうまく言葉を伝えられず、かんしゃくを起こす、噛みつくなどのトラブルも起こります。
援助するにあたり、注意するだけでなく言葉を補ったり、代弁したりすることが大切です。
3歳以上は、異年齢児との関わりも増えてくるため、保育士が主体にならずサポート側にまわるよう意識しましょう。
環境
環境の領域は、自然に触れるほか、図形や数などに興味をもつことも含まれます。
- 桜、プール、落ち葉、雪遊びなど、季節ならではの自然に触れる
- 動植物に興味をもち、観察したり飼育したりする
- 身近なおもちゃの形に興味をもつ
子どもに興味をもってもらうためには、まず保育士自身が、楽しむことが必要です。
「お空、きれいだね」「雪、冷たいね」と、美しさや感動を共有しましょう。
楽しそうな保育士の姿を見て、子どもの心も動き、興味関心をもちます。
言葉
言葉の領域では、発語、思いを伝える、話を聞くといった内容が入ります。
- ありがとうと感謝する
- 悪いときは素直にごめんなさいと謝る
- 相手の話を聞く
- 自分の思いを伝える
子どもの気持ちを代弁してあげることが重要です。
転んだときには「痛かったね」、物を拾ってもらったら「ありがとう」など、言葉で伝えることで子どもも保育士を見本とし、自分の気持ちを表現できるようになります。
表現
自分の思いを自由に書いたり作ったりし、創造性を養うことが入ります。
- 好きな色を使って塗り絵をする
- 粘土を使って自由に作る
- 友達に手紙を書く
表現の援助において大事なことは、否定をしないことです。
絵を描く、物を作るといった造形表現は、自由が前提。
「こうでなければいけない」「正しく描かなければいけない」ではなく、子どもが感じた感性を受け入れてあげましょう。
また、やりたがらない子に対しては、強制せず見守ることも、援助のひとつです。
保育五領域を活かすには「ごっこ遊び」がおすすめ

五領域をすべて網羅できる遊びが「ごっこ遊び」です。
ごっこ遊びの中で、五領域がどう関わっているのか、具体的に見ていきましょう。
たとえば、お店屋さんごっこをするとします。
それぞれの領域は、以下の通りです。
| 健康 | ・ハサミなどの刃物の正しい使い方を知り、安全に気をつける ・お店屋さんに必要な道具や材料を考える |
| 人間関係 | ・友達と相談・協力しながら作り上げる楽しさを味わう ・ごっこ遊びのルールを守りながら楽しむ |
| 環境 | ・実際のお店の仕組みを真似して再現する ・看板作りや値段設定を行う |
| 言葉 | ・お客や店員、それぞれの立場で必要な言葉を使う大切さを知る ・看板の文字や商品の値段などを書く |
| 表現 | ・それぞれの役になりきる、演じる ・身近な素材を使って製作する楽しさを感じる |
一例を挙げましたが、重要なことは「子ども達自身が自分で考えて行動するように関わる」です。
仮に、保育士が「ケーキやさんにします」「看板はダンボールで作りましょう」といった具合に、なんでも指定してしまうとどうなるでしょうか。
子どもは、自分で考えたり工夫することができないため、ごっこ遊びをしていても楽しさが半減してしまう可能性があります。
これでは、五領域を満たした保育とは言えません。
子どもの発想やペースに合わせて進められるよう、声かけや環境設定を考えていきましょう。
子どもの遊びは、保育士の関わり方で良くも悪くもなるので、指導案を立てるだけでなく、日々の保育にも五領域は意識して取り入れたいですね。
まとめ
五領域とは、子どもに養ってほしい基礎の力を指したものであり、健康・人間関係・環境・言葉・表現に分類されます。
五領域は、保育計画や指導案の作成の際だけでなく、日々の保育においても援助の指針となり役立ちます。
日々の保育に迷ったときには、五領域を見直し、これまでの保育を振り返ってみると良いでしょう。