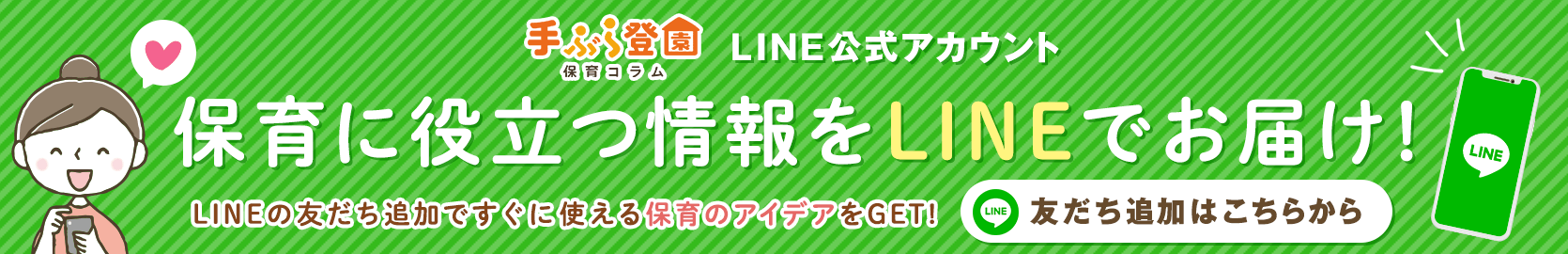保育の工作で子どもは成長する!ねらいとアイデア集をご紹介!

「保育で工作を行うねらいって何だろう?」「保育園で使える工作のアイデアを知りたい」と思う人も多いのではないでしょうか。
工作はものを作る楽しさだけでなく、子どもの想像力や集中力も養ってくれる、保育になくてはならない活動の1つです。
今回は、保育現場で工作を行うねらいと、工作のアイデアをご紹介します。さまざまな行事に合わせて年中楽しめるので、ぜひ現場の保育士ともアイデアを共有していきましょう。
保育現場で工作を行う8つのねらい
紙を切ったり、段ボールを組み合わせたりと、工作にはさまざまな種類があります。ではなぜ保育現場では、頻繁に工作をするのでしょうか?
最初に、保育現場で行う工作のねらいを8つご紹介します。きちんとねらいを理解して、子どものやりたいという気持ちをたくさん引き出しましょう。
何かを作る楽しさを味わえる
工作は、材料を組み合わせて何かを作る楽しさを味わえることが特徴です。必要な材料は画用紙やトイレットペーパーの芯、ペットボトル、紙コップなど、どこでも簡単に手に入るものが多く、お金もほとんどかかりません。
さらに、作った後はおもちゃとして遊べるので、子どもの満足度も高いでしょう。
集中力が高まる
工作には製作物の完成という分かりやすいゴールがあるため、子どもたちは集中して作業することができます。また、できあがったものを使って早く遊びたいという気持ちも大きいので、より集中して製作に取り組んでくれるでしょう。
集中力は、子どもたちが大人になる上で必要不可欠なもの。遊びをとおして、小さいときから身につけておくことが大切です。
動作が身に付く
工作には、紙を折ったりハサミで切ったりのりで貼ったりと、さまざまな動作が含まれています。折り方や切り方も製作物によって変わるので、子どもたちはできる動作がどんどん増えていくはずです。
製作物を作る経験を重ねるほど、より丁寧に早く作業できるようになります。保育園では日常的に工作の時間があるため、数をこなして成長していくでしょう。
達成感を味わえる
工作では、自分の力で1から製作物を作り上げる達成感が味わえることもメリットです。友達よりも先にできあがった場合は、分からなくて困っている子に教えてあげる機会もあり、お互いに助け合う心も育まれます。
1つのことを最後まで成し遂げるということは、大人でもそれほど簡単ではありません。子どものうちから、小さな達成感を積み重ねていくことが大切です。
道具に関心を持つ
普段使うハサミやのり以外に、穴を開けるためのきりや強力な接着剤など、今まで見たことのなかった道具を使うときもあります。新しい道具を実際に見て触れることで、子どもたちは道具自体にも関心を持つようになるでしょう。
ただし、新しい道具は興味を持ちやすい分、怪我にもつながりやすいです。使う前には必ず正しい使い方と注意点を伝えることを忘れないようにしましょう。
季節や文化について学べる
工作には、1年をとおして題材が溢れています。文化を学んだり、季節のものを実際に使ったりしながら保育ができることも工作の特徴です。
日本には四季があり、イベントも多数あるため、保育士にとっては準備が大変に感じることもあります。そのため先の見通しを立てて、計画的に題材を準備するよう心がけましょう。
コミュニケーション能力が向上する
工作中には、子どもたち同士で「何色にする?」「ここどうやるの?」「一緒に遊ぼう」とコミュニケーションを取りはじめます。他の子どもの製作物を見ることで、次はこうしようとアイデアが浮かぶこともあるでしょう。
保育士の声かけも大切ですが、工作をとおして子どもたち同士でも成長できます。特に5歳児は自分でできることが増えるので、手を出しすぎずに見守ってあげましょう。
思い出に残る
工作は作って終わりではなく、できあがった製作物で遊んだり飾ったりと、思い出としても残ります。楽しかった時間をみんなで共有できるのも、工作の魅力です。
作ったときの写真や映像を残しておくと、後で見返すこともでき、「あのときこんな遊びをしていたね」と思い出すきっかけにもなります。
保育に役立つ工作のアイデア集
保育園では工作の時間が多い分、アイデア出しに困ることも多いのではないでしょうか。
最後に、季節ごとに取り入れられる工作のアイデアをご紹介します。さまざまな行事の導入にも使えるので、ぜひ試してみてください。
春:マグネットちょうちょ(対象年齢:3歳)
マグネットを使って、不思議な動きをするちょうちょを作る工作です。磁石の反発を利用しているので、大人でもどこに飛んでいくか予想ができません。ゆらゆら動くちょうちょを見て、子どもたちも大喜びするでしょう。
春:ポリ袋でこいのぼり(対象年齢:3~4歳)
ポリ袋の中に入れる紙の色を変えるだけで、自分だけのオリジナル作品ができます。ふっくらと立体感があり、大きく見えるため、子どもたちも喜ぶでしょう。みんなのこいのぼりを並べて飾って、子どもの日を迎えるのも良いですね。
夏:スイカのうちわ(対象年齢:2~3歳)
夏を感じるスイカのうちわです。丸く切ったり種を書いたりと、とてもシンプルで簡単な作りなので、小さい子どもたちでも楽しく製作できます。完成した後は、たくさん使って暑い夏を乗り越えましょう。
秋:紙コップおばけ(対象年齢:3~5歳)
ストローから息を吹き込むと、モコモコおばけが出てくる様子を楽しめます。製作中はきりで穴を開けるので、取り扱いには十分注意しましょう。
秋:どんぐりのやじろべえ(対象年齢:3~5歳)
秋にしかない、どんぐりを使った工作です。外でお散歩をしたときに拾ったどんぐりを使っておもちゃを作るので、工作の時間も興味を持って取り組むことができるでしょう。
冬:煙突をのぼるサンタさん(対象年齢:5歳)
クリスマスが楽しみになるサンタさんの工作です。どうやって枕元にプレゼントが置かれるのか、工作をとおして想像力を働かせることができます。サンタさんが煙突をのぼる様子に、子どもたちもわくわくするはずです。
冬:おにのかぶりもの(対象年齢:2歳~)
2月の節分に合わせたおにのかぶりものです。土台は同じですが、好きな色の毛糸をのせれば、自分だけのかぶりものが完成します。実際にかぶって、みんなで節分を楽しむことができるでしょう。
まとめ
年齢は全体的に上がりますが、子どもたちのできることをもっと増やせる工作の時間。作る楽しさだけでなく、作る前の材料集めや作った後の発表会など、前後の活動にもつなげることができます。
季節に合った題材を取り上げれば、子どもたちが四季や文化を学ぶきっかけになるだけでなく、自分で完成させた製作物を使って季節のイベントを楽しむことも可能です。
土台は同じでも、色や形などに変化をつけて、子どもたち一人ひとりの個性が光る製作物を作りましょう。工作の題材に困ったときは、ぜひ今回ご紹介したアイデアも活用してみてください。