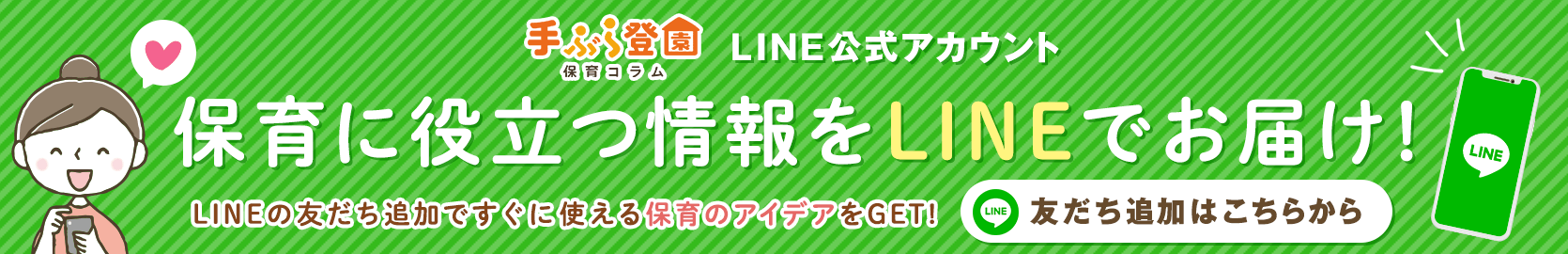保育園における新型コロナウイルス~感染症対策例~
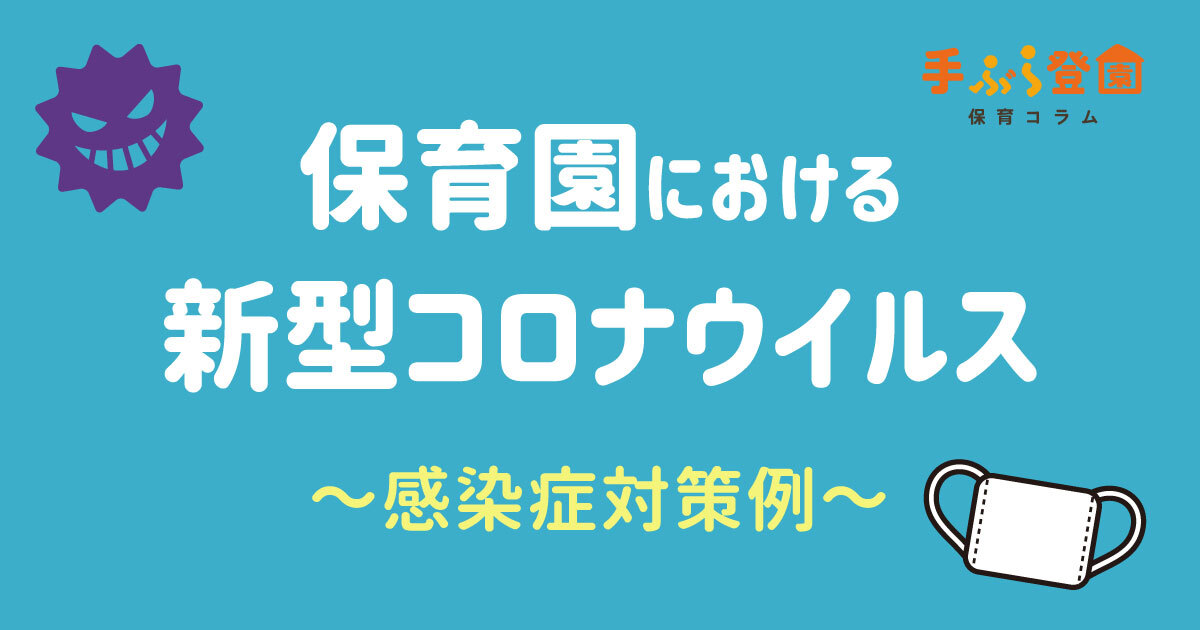
長期化するコロナ禍において、保育現場では感染症の正しい知識や情報を得て、臨機応変に対応することが求められます。
では、必要とされる知識や予防対策について学ぶにはどうすればよいのでしょうか?
保育園の経営支援・DX支援を行う株式会社 nt (ニト)では、保育士・保育園経営者が行うべき新型コロナウイルスへの予防対策をまとめた「コロナ対策大全」を公開しています。
コロナ対策大全とは
コロナ対策大全の目的
感染の基礎を理解し、保育園経営者としての心構えを持ち
引用:コロナ対策大全
新型コロナウイルスへの予防対策を行っていただくことを目的としています。
「コロナ対策大全」では、保育園が知っておきたい新型コロナウイルス感染症の予防・対策について、5つのステップで解説しています。
Step1 コロナを理解する
Step2 医療現場から学ぶ
Step3 保育園の感染症対策
Step4 チームでコロナ予防
Step5 シーン別対策事例
今回は参考までに、保育現場における感染対策の具体例について、「コロナ対策大全」の内容から一部抜粋してご紹介します。
感染症対策の基本
「コロナ対策大全」では、保育現場での感染症対策の基本として以下の3つが挙げられています。
- 全ての人が感染していると想定して行動する(スタンダードプリコーション)
- ウイルスのいる可能性の高さで保育室を分類し、保育室に応じて必要な行動を定める(ゾーニング)
- 上記の2つを行ったうえで、手洗い・消毒、マスク着用、清掃・換気といった基本的な感染対策を行う
感染症対策の基本を把握した上で、自園での方針や保育活動の具体的なシーンにおける予防対策方法を考えていくことが重要となります。
引用:医療現場から学ぶコロナ対策1 未知の病気を予防するために必要な基本的な考え方
来園者に対する感染症対策
職員以外の保育園関係者が来園するときに、コロナ感染のリスクを減らすためには、「場所の制限をする」、「人の制限をする」の2つが基本となります。
取り組んでいる園も多いと思いますが、発熱が認められる保護者の来園を禁止する、取引関係者の来園は1名までに固定するなどの対応が大事です。
大人への感染対策
1. 来園者全員感染している可能性があると考えて行動する
スタンダードプリコーションの考え方になります。感染症対策の基本ですね。
2. 取引関係者も含めて来園人数を制限する
来園者の数を減らすことで、ウイルスがいる可能性も減らすことができます。
3. 手指消毒、検温を徹底して行う
ルールとして必ず行ってもらうようにしましょう。従えない人は来園することを禁止するなどの措置をとります。
誰か1人でも許してしまうとやらなくても問題ないという意識が芽生えてしまいますので、厳しく判断しましょう。
4. ゾーニングにより来園者が行動できる範囲を決める
子どもが主に活動する保育室は、コロナのいる可能性をなるべく減らすため職員以外のの立ち入りを制限することも対策の一つとなります。
バスの送迎時の感染症対策

1.運転手となるべく接触しない工夫をする
例え毎日送迎してくれる運転手であっても、感染の可能性があると考えて接触感染や飛沫感染を防げるようにしましょう。
2. 後ろの扉から出入りしてもらう
運転手との接触を減らすためにバスに乗り降りする扉を運転手から遠いところにします。
3. 運転席にビニールシートを設置する
運転手からの飛沫を防ぐための工夫になります。
4. 座る席を固定化する
同じクラス、兄弟姉妹を近い席にするなど、なるべく接触する人を限定できるようにします。
5. 席の間隔を開ける
座席に余裕があれば、間隔を取ることで飛沫がかかりにくくなります。
保育活動での感染症対策

クラスでの保育活動
1. 保育活動場所を感染リスクが低くなるように設定
保育活動の中心となる部屋・クラスは、園児と担任の職員のみが入れるように制限し、不特定多数の人が入ることができないようにします。
出入り口での手洗い・消毒によってウイルスを持ち込まず、換気によってウイルスを減らす予防対策も一緒に行うようにしましょう。
このとき保育室を感染リスクの可能性で分類するゾーニングについて知っておいた方が良いです。
2. 60代以上の保育士は、接触する人数を減らす
感染症対策は、職員や保育士を守るためにも行われるべきです。
重症化リスクの高い60歳以上の職員がいる場合は、担当クラスを限定したり外部の人とのやりとりを減らすなど接触する人数を減らす工夫を行ってください。
3. 担当の保育士を固定化
園児と接する保育士や職員が多くなればなるほど、その分感染する可能性も高くなります。
担当する保育士を固定化することで、担当以外の園児への感染のリスクを減らします。
おもちゃや遊具
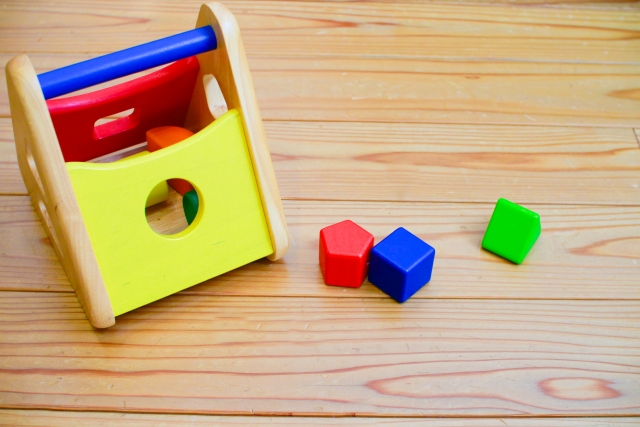
1. 口に入れたおもちゃは洗浄、消毒
ウイルスは感染者が触った物の表面に付いています。
保育園では、触るという行為だけでなく子どもたちが舐めたり口に入れたりする危険性があるので注意してください。
また、見落としがちなのが皮膚の傷から病原体が入り込む可能性があるということです。
傷口があれば絆創膏や包帯などで保護するようにしましょう。
2. クラスごとに使用するおもちゃを分類
接触感染を予防するためには、触った人の少なさがポイントになってきます。
つまり、触る人が少なければ少ないほど、感染の可能性も減ります。
クラスごとにおもちゃを分ける、おもちゃを触る保育士を決めるなどおもちゃを触る人を減らす工夫を行いましょう。
3. 遊具の使用後は消毒、清掃
遊具を使用した後は、手洗いを行うようにしてください。
遊具そのものについてもよく触れる場所は消毒や清掃を行います。
まとめ
コロナ対策大全では、医療現場での考え方を学んだ上で、保育現場への考え方に応用しています。
本記事では内容の一部を例としてご紹介しましたが、その他にも園内外での行事対策、保育室や給食所、トイレ、公園での感染症対策など、様々な情報が図解とともに分かりやすく解説されています。
基本的な感染症対策について学びなおせる内容となっているため、ぜひ一度ご覧ください。
株式会社nt(ニト)
保育園向け経営コンサルティングや女性向けウェルネスサービスを行う会社で、働く女性が何かをあきらめることなく、自分らしく生きることができる社会を実現するため活動をされております。
公式サイト:https://www.nt-inc.jp/