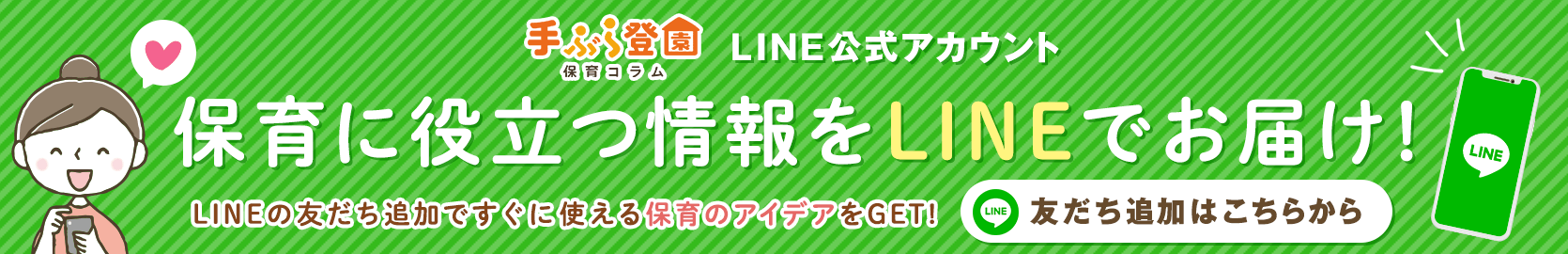全身を使った体操で保育を楽しく!おすすめの体操5選を紹介

「保育で行う体操のレパートリーをもっと増やしたい」「年齢別の体操ってどんなものがあるの?」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
体操で体を動かすことは、子どもの成長には欠かせません。体が大きくなるにつれてできる運動も増えてくるため、体操の種類を増やさなければならないこともあるでしょう。
そこで今回は、保育現場で行う体操のねらいと種類、おすすめの体操5選をまとめてご紹介します。元気に楽しく体操を行い、子どもたちの健康や成長につなげましょう。
保育現場で行う体操のねらい
大人になってからでも、定期的に体を動かすことで気分転換になったり、体の衰えを予防したりできます。同様に、子どもたちにとっても体操にはたくさんのメリットがあり、体を動かすことによって得られる効果は大きいです。
保育現場で行う体操には以下のようなねらいがあります。
- 全身の筋肉や関節をほぐして、体の柔軟性を高める
- 心肺機能を強くする
- 音楽に合わせて動くことで、リズム感が良くなる
- 体操をとおして他の子どもと触れ合い、コミュニケーション能力を身につける
このように、保育現場で行う体操にはいくつかのねらいがあります。健康に良いだけでなく、コミュニケーション能力の向上にもつながる体操。次に、上記のねらいを踏まえて、保育現場でできる体操の種類を見ていきましょう。
体操の種類
ここからは、保育現場でできる体操の種類を4つご紹介します。種類ごとの特徴を知って、保育目的に合った体操を選べるようにしましょう。
運動が苦手という保育士もいますが、事前にしっかりとやり方を落とし込むことで取り入れやすくなるでしょう。
準備体操
本格的に体を動かす前に行うのが、準備体操です。ウォーミングアップとも言います。準備体操を取り入れることで、筋肉や関節をほぐし、怪我をしにくい体を作ることが特徴です。
どんなに優秀なアスリートでも、準備体操には十分な時間をかけ、体の調子を整えます。特に冬場は、準備体操を行うことで体が温まり、心肺機能が上がる効果も期待できます。
子どもたちはすぐに走り回ったり、ジャンプをしたりしますが、それで終わりにせず、短い時間でも必ず足を伸ばしたり、体全体をひねったりして、準備体操をする習慣を付けると良いでしょう。
リズム運動
リズム運動とは、音楽に合わせて体を揺らしたりジャンプをしたりといった、誰でも日常的にできる動きのことです。子どもたちは、音に合わせて体を動かす楽しさを味わえます。
脳の働きを良くする効果があるともいわれ、0歳児の保育にも取り入れることが可能です。
リズム運動は、座ったまま体を動かして取り組むこともできます。ゆっくりめのリズムからアップテンポの音楽まで、いろいろと試してみましょう。無理をせず、リズムに乗せて体を動かすことが大切です。
ダンス
音楽に合わせてあらかじめ決められた振り付けを踊るダンスは、発表会や運動会などでよく行われます。
ダンスをとおして、身体能力だけでなく記憶力や協調性、コミュニケーション能力を養うことができるでしょう。発表会では衣装も用意されるため、子どもたちのテンションも上がります。
ダンスは、4~5歳児など、園児の中でも比較的大きい子どもたち向けの体操です。1人で考え込んでしまい行動することが苦手な子どもも、決められた振り付けを教えると安心します。
目標が明確になっていることで、ゴールに向かって努力しやすい点もダンスのメリットです。
リトミック
リトミックは、20世紀初めにスイスの作曲家・音楽教育家のエミール・ジャック=ダルクローズ博士が考案した体操です。
最初は音楽的能力を高めるものだと思われていましたが、後から集中力や思考力、協調性などあらゆる面で子どもの成長に役立つことが知られるようになりました。
リトミックは、ダンスのようにあらかじめ決められた動きをするのではなく、流れてくる音楽を聴いて考え、自分で表現することを大切にしています。そのため、一人ひとり表現方法が変わってくるでしょう。
大人になっても話を聞いて考え、行動しなければならない場面は多くあります。保育園のときからトレーニングをすることで、大人になったときに必要な能力を養うことが可能です。
保育に役立つおすすめの体操5選
最後に、保育現場で役立つおすすめの体操をご紹介します。すべて動画付きでご紹介するので、保育士への共有・指導もしやすいです。それぞれの対象年齢もあわせて見ていきましょう。
対象年齢がずれていると、体操ができなかったり簡単すぎたりして、やる気が損なわれてしまうこともあるので注意が必要です。
エビカニクス(対象年齢:0~2歳)
掛け声に合わせて、エビとカニになりきる体操です。簡単な振り付けなので、子どもたちは覚えていなくても、保育士を見ながらすぐに踊ることができます。
エビのように体を大きく曲げたり、カニのように両手と両足を広げたりして、特徴を掴みながら体を動かしていきましょう。
かえるのたいそう(対象年齢:0~2歳)
かえるになりきって、体を前後に動かしたり、ジャンプをしたりして全身を動かします。メインの運動の前の準備体操にぴったりです。
覚える振り付けも多くないので、保育士と一緒に楽しく体操できるでしょう。子どもは別の生き物になりきって体を動かすことで、笑いながら取り組めます。
どうぶつたいそう1・2・3(対象年齢:1~3歳)
5種類の動物が出てくる体操で、小さな子どもたちでも楽しんで参加できます。上半身をメインに動かすので、座ったままの子どもも一緒に楽しめるでしょう。
テンポが早すぎず、振り付けもとても簡単なので、幅広い年齢の保育に取り入れられます。「ニョロニョロ」「エッホッホ」といった掛け声も特徴的です。
はとぽっぽたいそう(対象年齢:2~3歳)
テンポがゆっくりなので、年齢が低い子どもたちでもまねをして踊ることができます。1番と2番は同じ歌詞と振り付けを繰り返すだけです。
大人でも「昔保育園でやったことがある」「はとぽっぽ、キューピーちゃんが印象的」など覚えている人が多く、保護者との話題にもしやすいでしょう。
しゅりけんにんじゃ(対象年齢:3~5歳)
忍者になりきって全身を動かす体操です。テンポもよく、かっこいい忍者になれるので、特に男児に人気があります。
女の子でも、くノ一がいることを伝えれば、忍者になりきりやすくなるでしょう。最後はテンポが少し早くなりますが、年齢が上がれば多少のスピードにもついてくることができます。
まとめ
成長して歩けるようになったり、走り回れるようになったりすると、体を動かすことに楽しさを覚えます。体操をすることで柔軟性、創造性、協調性、コミュケーション能力などが備わるため、積極的に取り入れていきましょう。
事前準備として体操を覚える必要も出てくるため、時間に余裕を持って取り組めるよう保育士に指導することも大切です。
特に発表会や運動会のためのダンス練習は、準備が大変なこともありますが、大人も子どもも楽しめるように笑顔で取り組んでください。