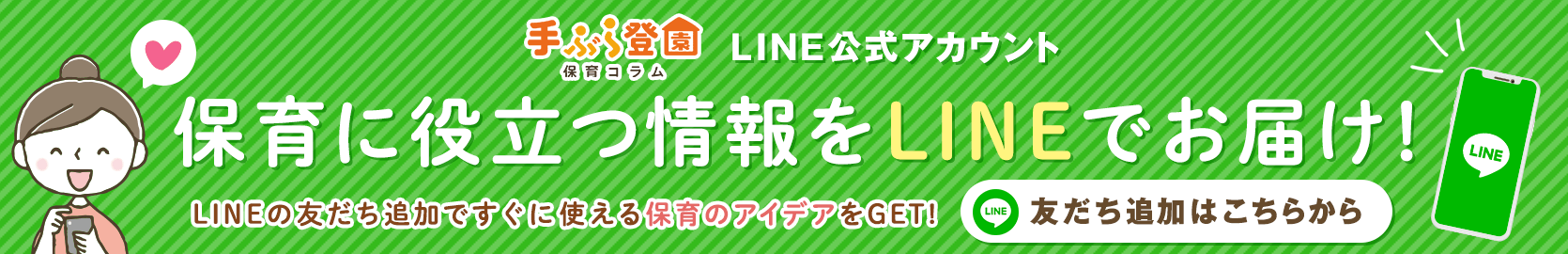保育ドキュメンテーションとは?メリットや活用法を紹介

保育ドキュメンテーションとは、写真などを活用して保育の「見える化」を行い、保育の質を向上させる手法を指します。
今回は、今注目されている「保育ドキュメンテーション」について、メリットや活用法を紹介します。
保育ドキュメンテーションとは?

保育ドキュメンテーションは、毎日の保育活動を写真や動画、音声やコメントなどで記録するものです。
こうした取り組みは、イタリア発祥の幼児教育法として行われており、保育活動のなかで、「子どもたちは何を学び、何を感じているのか」を保護者に向けて発信することを目的としています。
「記録、振り返り、予想、計画」の視点で考えることができるため、日本では「保育活動の見える化」といった意味合いで用いられることが多いです。
保育の質向上のほか、写真を共有することで保護者も場面をイメージしやすく、理解を得られやすくなるでしょう。
保育ドキュメンテーションのメリット

保育ドキュメンテーションを導入するメリットには、次のようなものが挙げられます。
子どもの成長を実感することができる
保育ドキュメンテーションに取り組むことで、子どもの成長を実感することができます。なぜなら、保育ドキュメンテーションは、子どもの活動経過を継続的に記録していくものだからです。
「楽しい写真を撮るだけ」ではなく、具体的な活動内容の写真やコメントを添えて記録するため、目に見えて子どもの成長を実感しやすく、職員同士でシェアすることもできます。
【例】
- 歩けるようになった
- 苦手なものが食べられるようになった
- ジャンプができるようになった
- 苦手なことにもチャレンジできるようになった
- 諦めずに最後まで頑張ろうとするようになった
- 夢中になれる遊びができた
子どもの成長が実感できることで、保育の仕事に対するモチベーションが高まり、結果的に保育の質の向上も期待できます。
保育の振り返りに役立つ
写真を残すことで、活動の振り返りがしやすくなる点もメリットです。子どもの表情や行動は、文字だけのテキスト記録だけではなかなかすべてを伝えることはできません。
保育ドキュメンテーションでは、文章だけではなく写真や動画も用いるため、子どもの表情や行動も鮮明に記録できます。
保育士は視野を広くし、できる限り全員の行動や表情を見ていますが、どうしても子どもたち一人ひとりの表情を、しっかり把握することは難しいです。
そのため、写真による記録を振り返ることで、「こんな表情をしていたんだ」「すごく盛り上がっていた」という、リアルタイムでは気づくことができなかった新たな気づきを得られるでしょう。
また、子どもの興味・関心事がわかると「この遊びをもっと展開していこう」などと、今後の保育活動の計画にも役立てられます。
保護者から理解が得られるようになる
保育ドキュメンテーションによる記録を保護者と共有することで、子どもの興味・関心や成長をより鮮明に伝えることができます。
言葉や文章では、表情や状況を誤解なく伝えることは難しいですが、写真や動画を共有すると、保護者もイメージしやすいです。
たとえば「今日、〇〇ができるようになって、すごくうれしそうでした」といった場合も、映像の有無によって保護者とのコミュニケーションのしやすさも大きく変わってきます。
映像があることで、家でも子どもの興味を広げたり、深めたりしてもらいやすくなるかもしれませんね。
保育ドキュメンテーションのデメリット

保育士の負担が増加してしまうことが、保育ドキュメンテーションを実施する上でのデメリットです。保育ドキュメンテーションは継続することが大切ですが、保育士は日々大量の業務を抱えています。
今の業務に加えて、新たに記録を書いたり、振り返りを行ったりすると、保育士の負担が増えてしまうことになりますね。「振り返りをする時間がとれない」施設もあることでしょう。
保育ドキュメンテーションを導入する際は、保育士の負担を増やさないよう、業務内容を見直すことも重要です。ICTシステムなどの業務効率化ツールの検討を視野にいれてみてもいいかもしれません。
また、写真や動画などの映像共有は、個人情報の観点から十分な配慮が必要となります。保護者からの理解を得るため、しっかりと説明をしたうえで取り組むようにしましょう。
保育ドキュメンテーションの作り方

保育ドキュメンテーションの作り方を3ステップで紹介していきます。
1.写真を撮る
保育活動の写真を撮影しましょう。重要なポイントは「子どものどんな姿を撮るか」です。ただ闇雲に撮影していては、意味がありません。
たとえば次のような瞬間を撮影するといいでしょう。
- 子どもが熱中している瞬間
- 子どもが楽しんでいる瞬間
- 子どもが試行錯誤したり、乗り越えようとしたりしている瞬間
- 子どもの良さが発揮されている場面
撮影したときには、子どもがどのようなことを話していたかも、コメントやメモとして残しておくと役立ちます。
2.記録する活動テーマを決める
今日の活動のなかから、テーマを決めていきましょう。1日のすべての活動を保育ドキュメンテーションにしても、ポイントがつかめずうまく活用できません。
【ドキュメンテーションの例】
- どんぐり拾い
- 色水作り
- ダンゴムシの観察
- 生活発表会の練習
子どもたちが興味のある活動にすると取りかかりやすいでしょう。最初は、ごっこ遊びや食事の時間など、日常の場面を切り取る形から始めるのも良いです。
3.写真につけるコメントを書く
写真にコメントをつけていきましょう。子どもの言葉や様子をそのまま言語化してみると、コメントをつけやすいです。
加えて「子どもがそこで何に心を動かしているのか」「どのような育ちがあるのか」といった、子どもの発達状況や活動のねらいを添えておくと、説得力が増して保護者にも理解されやすくなります。
保育ドキュメンテーションの活用法

保育ドキュメンテーションの効果的な活用方法を紹介していきます。
日誌として活用する
保育ドキュメンテーションを日誌として活用するのも有効です。写真つきなら、活動を見ていなかった他の保育士や園長にも、子どもの様子が伝わりますよね。
また、保育士の視点からみた様子などをコメントに残している際は、振り返りの手助けにもなります。
次の活動ではどのような配慮をしたらいいか、子どもの興味を広げるために、どんな活動を展開したらいいかなどがわかるので、翌日の保育活動につなげることができるでしょう。
記録を保護者と共有する
活動記録としてまとめたドキュメンテーションは、保護者と共有しましょう。写真を共有することで、活動中の雰囲気や子どもの様子をより詳細に伝えることが可能です。
また、継続的な取り組みから、子どもの成長を実感しやすくなり、保護者からも園の保育方針を理解してもらいやすくなります。担任と保護者のコミュニケーションにも役立ちますね。
掲示や配布を行う
活動の様子や子どもの制作物などは掲示しましょう。「こんな活動をしました!」と様子を壁に貼ったり、子どもの作品を掲示することも「見える化」のひとつです。
子どもの製作を掲示することで、子ども同士でも良い刺激になるでしょう。「僕(私)もしてみる」と活動意欲につながったり、自分の自信になることもあります。
まとめ

保育ドキュメンテーションを導入することで、保育の質が向上するだけでなく、保護者の理解も得られやすくなります。
子ども自身も成長を感じ、自信につながる可能性も秘めているため積極的に取り入れていきたいですね。
とはいえ、現場の保育士は多くの仕事を抱えていることもまた事実。
あまりにも負担が大きいと、せっかくドキュメンテーションを導入しても継続が難しいでしょう。導入する際は、負担が大きく変わらないよう配慮することも大切です。