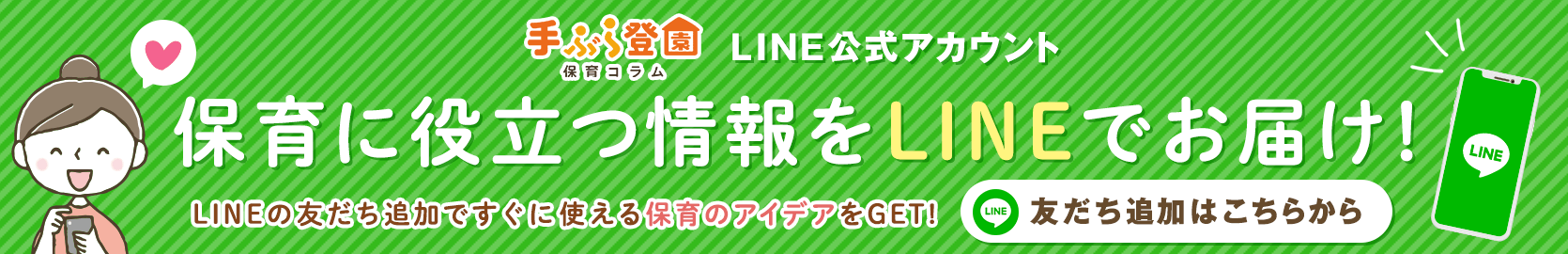保育で使える運動遊び12選!0~5歳年齢別で紹介

保育園や幼稚園での運動は子どもたちの体の成長に欠かせません。しかし、ただ難しくて辛いだけの運動をさせても子どもは楽しくないですし、体を動かすこと自体が嫌いになってしまいます。
保育での運動は、子どもに体を動かす楽しさを教え、好きになってもらうことがとても大切です。
子どもたちに体を動かすことを好きになってもらうために、遊びの中に運動を取り入れた運動遊びをしてみましょう。
年齢によって中心的に鍛えなければならない部位は異なりますが、運動遊びでは種類によって鍛えられる部位を変えられます。
また発達段階に合わせて運動遊びの難易度を変えられます。
日頃の遊びの中に運動遊びを取り入れて、どんどん子どもたちに体を動かすことを好きになってもらいましょう。
運動遊びを実践するときの3つのポイント

運動遊びを実践するときは、以下の3つの点を意識する必要があります。
- 多様な動きが経験できる遊びを取り入れる
- 楽しく体を動かす時間を確保する
- 発達の特性に応じた遊びを提供する
文部科学省の幼児期運動指針には、幼児期の運動は「一人一人の幼児の興味や生活経験に応じた遊びの中で、幼児自らが体を動かす楽しさや心地よさを実感することが大切である」と書かれています。
出典:幼児期運動指針
幼児期は運動機能をはじめ、体の機能が著しく発達していく時期です。
そのため、遊びのなかに運動を取り入れた「運動遊び」を実践することで、さまざまな体の動きを経験し、会得する必要があります。
運動遊びのねらい

運動遊びの種類によってねらいはさまざまですが、以下のような項目をバランスよく取り入れましょう。
- 遊びを通じて運動刺激を受けることで、体の動かし方や力のコントロールを身につける
- 「走る」「ジャンプする」「転がる」「ぶら下がる」「くぐる」「よける」など、多様な動きを遊びのなかで経験する
- 柔軟性や瞬発力、バランス能力などを養い、身体感覚を高める
- 体全体を動かす気持ちよさや楽しさを感じる
- 自ら体を動かそうとする意欲を育む
- 友達と共に運動遊びを楽しみながら、コミュニケーション力や社会性を身につける
- 成功体験を自信につなげ、自己肯定感を高める
子どもによって成長スピードは異なります。
できなかったことができるようになった喜びを感じさせたり、より高度な動きにチャレンジさせたりと、子どもに合わせて運動遊びのねらいを変えることも、体を動かすことを好きになってもらうためには大切です。
保育の現場で使えるおすすめの運動遊び12選

0歳から5歳まで、年齢別にオススメの運動遊びを紹介します。
ただし、必ずしもその年齢なら上手くできなくてはいけないわけではありません。子どもの発達段階に配慮して難易度を変えていきましょう。
【0歳児向け】赤ちゃん体操
<遊び方>
- 子どもを仰向けに寝かせる
- 歌のリズムに合わせて手足をグーンと伸ばしたり、手を開いたり閉じたりして体を揉む
大人とのふれあいを楽しみながら、体を動かす楽しさを感じられる体操です。
【0歳児向け】ぽっとんおとし
<遊び方>
- 折り紙を丸め、子どもたちが口に入れてもいいようにテープを巻く
- ペットボトルなどの入り口が細い容器に丸めた折り紙を上手く入れる
指先の細かい動きを習得できます。
【1歳児向け】おつかいありさん
<遊び方>
- 先生は子どもを膝の上に乗せる
- リズムに合わせて子どもを上下に動かす
- タイミングを合わせて子どもを膝の間に落とす
上下の動きで不安定な経験をさせ、バランスをとるための基礎を作れます。
【1歳児向け】サーキット遊び
<遊び方>
- マットやフラフ-プなどで障害物をつくる
- 子どもたちが障害物を並べたコースを遊び回る
楽しいだけでなく、コースによっては全身の運動能力を鍛えられます。
【2歳児向け】しっぽ取りゲーム
<遊び方>
- 先生は人数分のタオルや新聞紙でしっぽを用意し、子どもたちが走り回れる範囲を決める
- 先生はズボンにしっぽを入れる
- 先生が「よーいスタート!」の合図をしたら、子どもたちは先生のしっぽを取りに走る
- しっぽを取られたら子どもたちの勝ち
走り回ることによって脚の力や体力を鍛えられます。
【2歳児向け】飛行機体操
<遊び方>
- 両肘を床につけ、体を起こし、目線を前にする
- この姿勢のまま相手と向き合い、じゃんけんをする
- じゃんけんで負けた人は両手・両足を床から離し、飛行機のようなポーズをする
姿勢をよくする背中の筋肉が発達するので、良い姿勢を維持する力を養えます。
【3歳児向け】だるまさんがころんだ
<遊び方>
- オニを1人決め、オニは木や壁を向いて他の子に背を向ける
- オニじゃない子はオニに近づき、タッチする
- オニは「だ~る~ま~さ~ん~が~こ~ろ~ん~だ!」のリズムに合わせて他の子たちの方を向く
- オニが振り向いたら鬼じゃない子は動きを止める
- 動きを上手く止められなければアウト、タッチできれば他の子の勝ち
一瞬の動きに合わせて自分の体をコントロールするため、瞬発力やバランス感覚を養えます。
【3歳児向け】かみなりゲーム
<遊び方>
- 床に仰向けになる
- 先生が「ゴロゴロゴロゴロ」と言いながら子どもたちのおへそを狙う
- 先生が「ドカン!」と言ったら子どもたちは先生におへそを取られないようにうつ伏せになる
横になったまま動くので、背中側の肺が広がりやすくなり、呼吸器が発達します。
【4歳児向け】新聞タオルキャッチ
<遊び方>
- 新聞紙で細長い棒を作る
- 2人ペアになり、棒を1本ずつ持つ
- 1人はタオルを友達に投げ、もう1人は棒でキャッチする
ペアでタオルをキャッチしあう運動あそびです。慣れてきたら距離を離したり棒を短くしたりして難易度を上げることもできます。
【4歳児向け】動物なりきりポーズ
<遊び方>
- 先生が動物を指定し、子どもたちがその動物のポーズを真似する
- 動物のポーズを真似したまま、いろんなコースを動き回る
動物によって特徴的な動きが異なるので、全身の運動能力を高めることができます。
【5歳児向け】ピンポン玉運びレース
<遊び方>
- おたまなどにピンポン玉を入れる
- ピンポン玉を落とさないようにおたまを持って運び、中間地点で折り返す
- 戻ってきたら次の子におたまを渡す
- 一番早く最後の子まで戻ってこれたチームが勝ち
レース形式で楽しみながら、バランス感覚を養うことができる運動遊びです。ピンポン玉を入れる容器の大きさや深さで難易度を調整することができます。
【5歳児向け】ボール運動遊び
<遊び方>
- 相手とボールを転がし合ったり、バウンドさせながら相手のところまでボールを届ける
- 慣れてきたらバウンドを大きくしたり、バウンドせずにキャッチさせる
ボールの扱いに慣れるだけでなく、相手と一緒にやることでコミュニケーション能力も高められます。
まとめ

幼少期のうちから運動能力や体を適度に鍛えるのは大切なことです。
とくに、保育園や幼稚園に通うような年頃は体の成長や神経の発達が著しく、今後にも大きな影響を与えます。
さらに、体を動かすことで体だけでなく心も育ちます。
仲間とのコミュニケーションの喜びや勝ち負けへのこだわりを体験させ、心の動きを感じさせてあげることが大切です。
体の発達にも心の成長にも欠かせない運動を遊びの中に取り入れることで、楽しく運動習慣を身につけていきましょう。