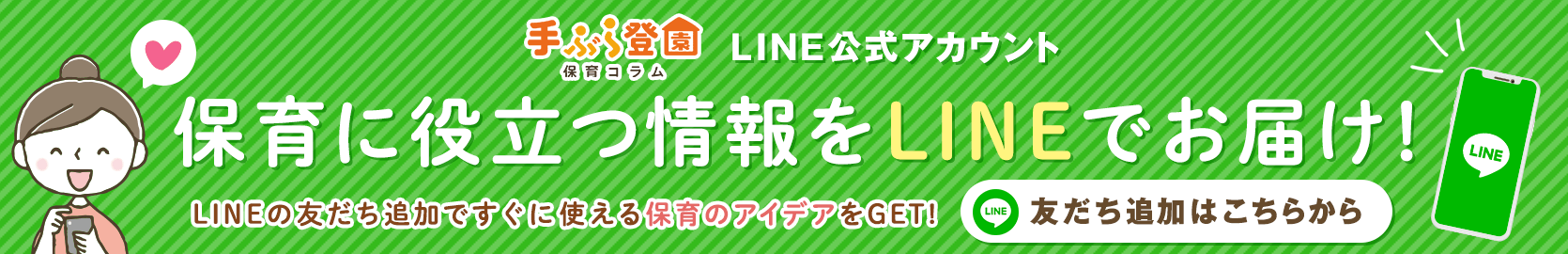保育士の研修はどんな服装で向かえば良い?シーンごとにおすすめを紹介

社会人である以上、他の職業と同様に保育士の服装もTPOを意識する必要があります。
TPOをわきまえた服装をすることで第一印象が良くなりますし、子どもを預ける保護者の信用にも繋がるでしょう。
しかし、保育士が研修を受ける際には社会人としてスーツで行くのがよいのか、それとも保育時のようにカジュアルな格好で行くのがいいのか悩むものです。
この記事では研修の内容に応じて、保育士が着ていくべき服装を解説します。普段とは異なる基準の服装選びやTPOへの配慮を理解するようにしましょう。
保育士の研修にふさわしい服装

保育士の研修にふさわしい服装は、受ける研修の内容によって異なります。
なにかしら保育園側から指示があるはずなので、プリントなどを確認しましょう。
どうしても判断に迷う場合は、先輩や園長に質問するのも一つの手段です。
先輩も研修が初めての可能性があるため、複数人に聞いてみましょう。
スーツでなければならないケースはめったにありません。
しかし、だからといって派手な服装やカジュアルな服装が適しているというわけでもないので、研修の内容ごとに適した服装を確認しておきましょう。
また、上履きやエプロンを持っていくのかどうかの確認も必要です。
座学系の研修を受ける場合
座学系の研修を受ける場合、オフィスカジュアルのスタイルを参考にするのがおすすめです。
研修内容が「発達障がいを学ぶ」「主任保育士研修」「マネジメント研修」などの場合、体を動かすことはほとんどありません。オフィスカジュアルを参考にし、キレイ目でラフすぎない服装で行くようにしましょう。
よく分からない場合は、ビジネスの場に適したジャケットを羽織るだけでもオフィスカジュアルなスタイルのように見えます。
また、体をあまり動かさないので季節によっては寒いときもあります。羽織れるものを持っていくのも忘れないようにしましょう。
座学系の研修を受ける場合にふさわしい服装の具体例
- スーツ
- 開襟シャツ
- 白や目立たない色のTシャツにジャケット
- ジャケットに合わせたチノパンやスキニー
- ローヒールのパンプス
- ブラウス、カーディガン、スカート
体を動かす系
体を動かす系の研修の場合、ストレッチ素材など動きやすいものを選ぶようにしましょう。
研修内容が「リトミック研修」「抱っこの仕方研修」「救命救急研修」などの場合、実際に体を動かして学ぶことがあります。
普段着などのようにカジュアル過ぎるのはよくありませんが、激しめに動いたり汚れたりしてもいい服を選びましょう。
体を動かす系の研修を受ける場合にふさわしい服装の具体例
- ジャージ
- Tシャツに動きやすいジーンズ、チノパン、ストレッチデニム
- 派手すぎないスニーカー
保育士の研修にふさわしくない服装

保育士の研修に限ったことではありませんが、色や柄が派手なものは研修にふさわしくありません。
研修は学びの場であると同時にビジネスの場でもあります。
社会人としてふさわしい格好をするようにしましょう。
たとえば、動きやすい服装といってもひらひらしすぎるスカートは研修に不向きです。
ほかにも、肌の過剰な露出は言うまでもなく、サロペットやガウチョ、スカーチョなども派手な服装に含まれます。
普段着を選ぶような感覚でコーディネートをしないように気をつけましょう。
研修時の服を選ぶときのポイント

保育士が服を選ぶときに最低限抑えるべきポイントは以下の4つです。
- 動きやすいもの
- 汚れてもいいもの
- 装飾がないもの
- 露出度が低いもの
動きやすいもの
座学系でも動く作業がある可能性もあるので意識しておきましょう。
動くにしても動かないにしても、ズボンが無難です。
ストレッチ性のある素材で作られたズボンで研修に行きましょう。
フード付きの服は動いてるときに首が絞まったり、ほかのものに引っかかったりして危険です。フードが付いていない服を選びましょう。
汚れてもいいもの
研修中でも実際に子どもたちと接する機会を設ける場合もあります。
高級なものやお気に入りの普段着を着ていくのは避けるべきです。
また、汚れていい服というのは汚い服のことではありません。
衛生上の問題がないような清潔感がある服を選びましょう。
装飾がないもの
装飾はちょっとしたはずみで気づかないうちに破損する可能性があります。
そして、破損したものを子どもが飲み込む危険性もあります。
また、硬かったり尖ったりしている装飾が服についていると、子どもと接するときに子どもを傷つけてしまうかもしれません。
基本的に装飾品は外しておきましょう。
露出度が低いもの
仕事の場である以上、露出度の抑えた服装を意識してください。保護者や先輩保育士の中には、子どもたちの前で露出度の高い格好をすることを好ましく思わない人がほとんどです。
保育の場では肌の露出が多ければ、自分も怪我をする危険性も考えられます。何より、子どもたちや保護者にだらしない印象を与えかねません。社会人の最低限のマナーとして露出度の高い服装は避けましょう。
研修時の髪の毛の色や長さ

身だしなみといえば、服装だけでなく髪型もおろそかにしてはいけません。
髪の毛は、顔のパーツの中でも人の印象を最も大きく変える効果があります。
保育や研修にふさわしい服装に合わせて髪の毛の色や長さを整えることで、よりTPOを配慮した見た目となるでしょう。
髪の毛の色
どのような内容の研修だったとしても、地毛の色もしくは黒、暗めの茶色で受けるのがベストです。
もし地毛の色が黒や茶色よりも明るく、目をつけられないか心配な場合は黒や茶に染めるか、事前に研修先や研修担当の先生に連絡しておくのがオススメです。
髪の毛の長さ
基本的には肩にかかるくらいまでの長さにするか、長い方はひとつ結びをしましょう。
長い髪の毛を結ばずに保育をしてしまうと、子どもを抱いたときに髪の毛の先が目に入ったり、顔の皮膚に当たって傷つけたりする可能性があります。
また、子どもたちが引っ張ったり、つまずいたり、子どもたちの食事の援助中に髪の毛が入ったりしてしまいます。
衛生面や安全面でもよくありませんし、長い髪は視界の範囲を狭め、子どもたちを見渡しづらくなるため、後ろでしっかりと結びましょう。
研修時に押さえておきたい見えない部分の身だしなみ

服装や髪型といった外見だけに気を遣いすぎて、当日うっかり忘れてしまうものがあります。
それは以下の4つです。
- ハンカチは持っているか
- ティッシュは持っているか
- 爪は短く整えられているか
- 糸のほつれやとれかけのボタンはないか
保育士が見た目を気にして、見えない部分の身だしなみを見落としてしまってはいけません。
とくに、爪は衛生面や安全面に直結するので忘れずに整えましょう。
まとめ

TPOに合わない服装で研修に参加してしまうことは、社会人としての信用を失いかねません。研修の内容を集中して学び、保育の質を高めるためにも万全の準備をして受けるようにしてください。
服装をはじめとした、目に見えるポイントを押さえるだけでなく、見えない部分の身だしなみにも注意が必要です。
園の一員として意識を高く持った服装を心がけ、いつ子どもたちに見られても胸を張っていられる格好をしましょう。