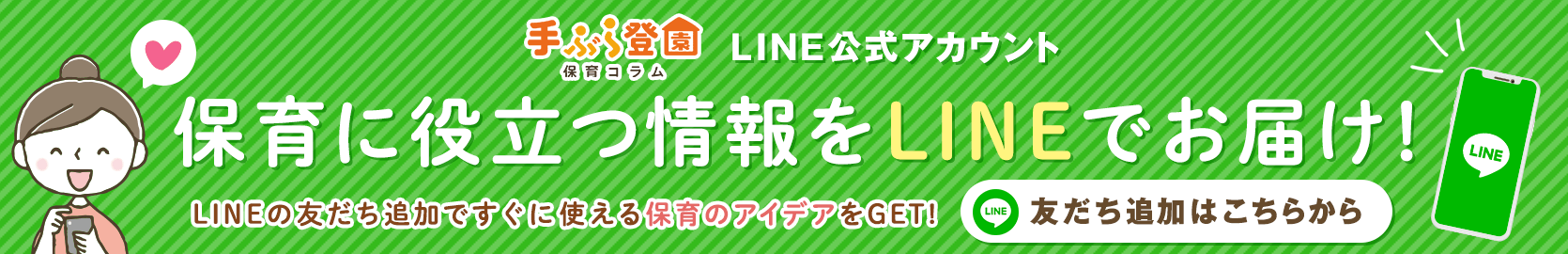男性保育士が語る多様性と未来—あたらしい保育イニシアチブ2024

保育分野の未来を拓くイベント『あたらしい保育イニシアチブ2024』が東京大学で開催されました。本コラムでは、男性保育士3名が登壇し保育の多様性や、少子化社会における保育の課題について話し合いが行われたセッションをご紹介します。
保育の多様性を語る~男性保育士から手ぶら登園~
このセッションでは、「保育の多様性を語る~男性保育士から手ぶら登園まで~」をテーマに、3名の男性保育士が保育や子育ての課題について意見を交わしました。
登壇者には、5人の子どもの父親であり最近保育士免許を取得したタレントのつるの剛士さん、3人の子どもの父親で保育の専門家として活躍する小崎恭弘先生、そして子育て支援サービスを提供するBABY JOB株式会社の代表上野(保育士免許を保有)が参加。それぞれの立場から、今後の保育のあり方や子育てに関する考えを共有しました。
拓かれた保育現場にしていきたい
つるの剛士さん:僕が芸能生活25周年を迎えるという節目の年に、ちょっと人生を振り返ってみた時に「子ども」というキーワードが大きなテーマとしてあるなと気付いたんです。5人の父親をしていたり、当時では珍しかった育児休業を取得したりで、子育てに関する話をさせていただく機会が結構あって。
今後の人生も「子ども」ということが1つテーマになっていくんだろうなと思ったときに、専門的な学びをしたいと思ったんです。それで、短大に入学して保育の免許を取得しました。免許を取った後も大学に入って、子どもの心理学を学んでいます。
僕が保育業界に入って思ったことは、自分が思っていた以上に閉鎖的なんだなと感じたんですよ。もうちょっと横の繋がりがたくさんあって、みんなで子どもたちを見ていこうね、みたいな社会なんだと思っていたので、ちょっと驚きました。
だから僕みたいに新参者というか、30年ぐらい芸能界という保育とは違う仕事をさせてもらってから入ることで、ものすごく新鮮な視点で、かつ俯瞰的に色んなこと見られると思っています。 そこで感じたことを発信していけたらいいなと思っています。
上野:発信していくのはいいですね!子育てをしている人が減っているので、もちろん子育てしていない人が子育て世帯に接する機会は少なくなっていきます。子育て世帯の理解や子どもの理解のためにも、僕ももっと開放的になったらいいなと思っています。
小崎先生:昭和50年ごろは半分以上の世帯に子どもがいたんですよ。昭和40年ごろだともっと多くて6割ぐらい。それが、今の1番新しいデータだと、全世帯の2割以下にしか子どもがいないという状況。この数字は18歳以下の子どもを全て含むから、未就学児で絞ると数パーセントしか子どもがいない。だから本当に子どもと関わる機会はどんどんなくなっていると思いますよ。
つるの剛士さん:やっぱり強制的にでも、子どもと関わる時間や場所を作っていくのは、僕はすごく重要じゃないかなと思います。
小学校から見た幼保小の接続について
上野:小崎先生は小学校の校長をされていたと思いますが、幼保小の接続に対して小学校側からみて何か感じることはありますか?
小崎先生:幼保小の接続は大事よね。なので小学校の校長になって、よし接続の部分を頑張ろうと思ったんですが、小学校の業務が忙しすぎてできなかった。例えば、0歳の子が保育園に入園してきたときに産婦人科に行って、この子はどんな子ですか?どうやって生まれてきましたか?と聞きに行くことはないですよね。小学校だとこれが必要になるんです。
でも多ければ地域の数十の幼稚園・保育園から子どもが入学してくるので、全てと深く連携するのはできなかった。ただ、こども家庭庁も発信しているように、幼保・小学校と途切れるのではなく、ずっと継続して子どもを育てていける環境を作ることは、今後求められるし大切だと思います。
あと幼保と小学校だと文化が違いすぎるので、そこはもうちょっと交流をしてお互いの理解を深めないといけないかなとは思います。
今後の保育施設は選ばれるようになっていく
上野:今の保育における課題は何だと思いますか?
小崎先生:少子化も超えて人口減少の社会の中で、やっぱり保育は何ができるのか、子どもをどう育てていくのかというのが1番の大きなテーマだと思います。
それと保育施設の定員割れも大きな問題。 こども家庭庁が出した1番新しいデータだと充足率が毎年1パーセントずつ減っている状況ですね。地方とかだと75%、県全体で25%の定員割れが起きているというのは大きな問題だし、取り組んでいかないとと思っています。
ただ、定員割れと言いながらも保育がなくなるわけではないので、そういう意味では少子化と保育施設が増えた中では適正な競争が起きていますね。今後は保護者が園を選ぶ形になると思う。選ばれる園とそうでない園がはっきりしていくんだろうね。
保育はサービスではない、保護者と共に保育現場を築く
つるの剛士さん:そういえば最近思ったことがあります。今息子が自転車にはまっていて、近所のBMXの教室に通っているんですが、 子どもたちも保護者も体を使って「うわーっ」って元気よく参加しているんですよ。それで、子どもたちがちょっと転んで、 血が出たり、骨が折れたりみたいなことがあっても、保護者がサポートに入って「大丈夫、大丈夫よ」といって、その習い事を続けてるんです。あの姿を見ていたら、 これは保育と融合できないものなのかな?と感じるんですよ。
小崎先生:それは本当に大事な視点だと思います。その教室では、子どもが怪我してもあまりトラブルにならないんでしょ?骨を折っても、大きな怪我しても、それは保護者も子どもも主体的に関わっているから当事者意識があるんだと思います。
だから何があっても自分の責任だと思っているし、そこで得られるものも自分の物だと思うけど、今保育が「サービス」になってしまっていて、 お金を出してるからとやってもらって当然。という雰囲気がある。これは学校も本当にそう。
保育はやっぱり保護者と一緒に、子どもを育てていくっていうような意識とかスタンスが大事になってきます。そういう意味では、主体性とか主体的にということを大切にしている理由はそこにもあると思う。
つるの剛士さん:確かに保育はサービスじゃないですよね。
小崎先生:だから保育はそれこそ頑固さも必要で、「ここは譲らない!」とか、「これは私たちの園ではしませんよ!」ということをちゃんと発信していかないといけない。
保護者と一緒にこういう風に子どもを育てていきたいであったり、こんな子どもたちになってほしいだったりをより明確にしていくことが大事なのかなと思います。
個性を活かしてチームで支える新しい保育の在り方
小崎先生:僕の夢は、男性保育士が3割以上いる園が増えたらいいなと思っています。知り合いの園だとすでに男女が半々というところもあります。
男性保育士の何が良いかというと、男性も育児ができるというモデルが1つと、もう1つ、男女が共に子どもを育てるというモデルだと思っています。小さい頃から子どもたちがそのモデルを見ていたら、それが当たり前になるんじゃないかなと思っています。
上野:でも男性が保育士として働くのは大変ですよね?着替えるところがなかったり、保護者から乳児のおむつ替えをしてほしくないと言われてしまったり。どうですか?
つるの剛士さん:保育のジェンダー的な問題もあると思うんですが、保育士の仕事はおむつを替えることだけではないじゃないですか?虫取りが得意な先生、ピアノが得意な先生、絵が得意な先生、そこはもう別にジェンダーとかいうこと関係なくそれぞれの強みを活かすだけだと思う。〇〇は不得意だけど、〇〇は得意な先生がいるっていう考え方だけだと思います。
上野:保育の文化の中に個人の強みを活かすみたいなことは、あまり聞かないなと思っています。その発想があったらもっと個人も活かされそうですね。
小崎先生:それはね、保育という枠組みが今まで担任がすべてやらないといけないという個人プレイヤーを育てていく文化があったのが原因だと思う。ただ今の保育には、確実にチームプレーが大事。保育の時間が長くなり、保育内容も業務も多様化している中で、求める保育者像だけがすごく単純化してしまっている。
今おっしゃるみたいに、その人の強みも弱みも分かったうえで上手く配置していくことが必要になると思いますね。保育士でマネジメント研修が入っているのはそういう意味だったりします。
子どものパワーを活かして笑顔が広がる保育の在り方
小崎先生:保育の課題は何?と言った時に、少子化とか人口減とかマイナスなことに対応しないといけない危機感で話すと、楽しくないんだよね。 だからやっぱり子どもが中心。皆さん子どもに関わると楽しいじゃないですか。 ものすごく面白いし、腹抱えて笑えるしという、そういうポジティブなことを話していきたい。
僕は、子どもは人と人とを繋いでいく存在だと思っています。子どもたちとお散歩に行ったら、やっぱり地域の人たちみんな声をかけてくれるんですよね。 これが子どものパワーだと思うし、もっとその力を存分に発揮できていければと思うんですけどね。
上野:子どものパワーを使うというのは、ポジティブで楽しいですね。
つるの剛士さん:子どもに遊びを教えてもらうのがいいですよ、皆さん真面目すぎて遊んでないもん。大人がまず楽しんでなきゃいけないから、 まず自分たちがどう遊ぶかということがすごく大切なような気がしています。
まとめ
保育の未来を考える中で、多様性や主体性、そして保護者との連携の重要性が改めて考えさせられるセッションとなりました。また、保育の現場がより拓かれた場となり、誰もが関わりやすくなることへの期待も感じられます。
これからの保育をより良いものにしていくために、保育に関わるすべての人が当事者意識を持ち、それぞれの役割を果たしながら一緒に考えていきたいですね。